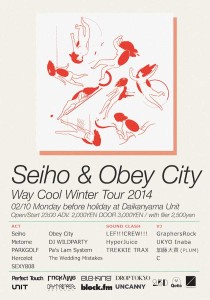- EVENT REPORTSDecember/14/2013
-
【Event Report】Red Bull Music Academy Weekender Tokyo “Beacon in the City” – 2013年11月2日 at SHIBUYA WWW
1998年に設立され、有名無名に関わらず才能あふれる若きアーティストたちを支援してきた世界的な音楽学校として知られるRed Bull Music Academy。その設立15周年を記念して11月に開催されたイベント<Red Bull Music Academy Weekender Tokyo>は4日間に渡り、実験的でユニークな試みを支援し続けてきたRed Bull Music Academyの精神を体現する催しとして開催され、盛況の内に終了した。今回は、インターネットラジオ局dublab.jpの協力によって開催された<Beacon in the City>の模様をお届けする。
dublab.jpは、インディペンデントな姿勢でポジティヴな音楽、アート、カルチャーを広めることを目的として始まった、LA発の非営利ウェブ・ラジオ・コレクティヴ、dublabの精神を受け継ぎ、日本のインディペンデント・ミュージックを世界に発信する為に設立されたインターネットラジオ局だ。その出張企画<Beacon in the City>が、今回海外から招いたのはdublabの中心人物、Frostyと、LAのビートシーンの中核であり、ジャンル不問のユニークな音楽によってリスナーを魅惑し続けてきたDaedelus、そしてその2人のユニットであるAdventure Time。日本からは、OMSB & Hi’Spec (from SIMI LAB)、鈴木勲 & DJ Kenseiによるスペシャルセッション、イルリメのDJがこの夜を盛り上げた。
<Beacon in the City>は、トーク、ライブ、DJが代わる代わる展開する実に多彩で、ラジオ番組そのもののようなイベントであった。この日は、Frostyとピーター・バラカン氏、そしてdublab.jpの運営に携わる音楽評論家、原雅明氏の三者によるラジオと音楽に焦点を当てたトークショーからイベントが始まり、それは音楽とラジオに潜む可能性と魅力について実に示唆に満ちた内容だった。ここでその内容について詳しく触れられないことは残念だが、ともかくライブの一番手はOMSB & Hi’Spec(from SIMI LAB)だ。
前半はHi’SpecのDJプレイ、後半はOMSB & Hi’Specによる特別なライブセットという構成で、ヒップホップとクラブミュージックの両面において先頭を走る両者の姿が浮き彫りになるステージだった。Hi’SpecのDJはダブステップ、ガラージ、R&B、レアグルーヴ、モダンジャズなど様々な音楽が正にdublab〜ラジオのような縦横無尽なミックスが駆け巡り、ライブセットはHi’Specによって過激に再構築された『Mr. “All Bad” Jordan』のトラックの上を、OMSBが声をダブ・エフェクトで操作しながらラップしていくスタイル。そこには2010年以降の日本のヒップホップを貪欲に更新していこうとする姿勢が感じられた一方、最近手に入れたというKORGの機材を駆使し、無邪気に声で遊ぶ子供のようなOMSBの姿は、Simi Labではコミカル面担当といった趣ながらクレバーなトラックメイカーの側面も併せ持つ彼の、無邪気と狂気の狭間をすれすれでいくクリエイティビティの発露といった感もあり、計算高いトリックスターよりもこのタイプが予測不能で一番面白いのかもしれないと改めて思ったのであった。終始一貫、フロアの温度を上昇させ続けた実に熱いプレイの連続だった。
フロアの勢いを受け継ぎながら会場の熱はどこにいくのかと思えば、次に現れたのはイルリメ。実にいつも通りの飄々とした雰囲気で、自分の解説を交えたラジオスタイルのDJは、Pusha-Tから始まりFour Tet、Rhyeなど最近気になった曲をひたすらかけていくところから始まり、Daft Punk「Get Lucky」のスマッシュヒットから野口五郎のディスコ「Music in My Pocket」、ジャイアント馬場の天然スクリュー(笑)「満州里小唄」まで、笑いも交えながら進む。
DJだけでなくヒップホップ、シンガーソングライターとしても活躍するイルリメのとらえどころのなさ、ジャンル不問の音楽採集家といった趣も含めてdublab的と言えるならば、鈴木勲 & DJ Kenseiによるこの日のためのスペシャルセッションもまたdublab的。日本の音楽のアンダーグラウンドでドープな層を掬い取り、焦点を当てたような趣に満ちた演奏だった。渡辺貞夫、富樫雅彦、菊地雅彦らとの共演、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの一員だった経歴を持つ、日本ジャズ界でも最高齢のジャズベース、チェロ奏者である鈴木勲と、80年代後半から90年代にかけてヒップホップDJとして活躍してきたDJ Kensei。80歳を迎えてもKILLOR-BONGとの共演などで気炎を吐く生粋のジャズプレイヤーと、かつては’INDOPEPSYCHICS’のメンバーとして、現在のLAビートシーンとも共鳴するようなジャンル不問の先鋭的なビートミュージックを生み出していたDJとの初共演は、吉と出たか凶と出たか。
DJ Kenseiが’INDOPEPSYCHICS’のトラックを彷彿とさせるブレイクビーツ、エレクトリック・マイルス的なトランペットからレアグルーヴのカットアップまで様々なネタで予測不能な展開を見せるのに対して、鈴木勲はチェロ1本、生粋の現場主義者として幾多の修羅場を潜り抜けてきた、自身の腕と感覚への絶大な自信を感じさせる即興的な演奏によって瞬時にネタに反応し、音を返す。当意即妙ときには一触即発の緊張感を携えながら、プレイヤー同士にしか分からない言語を用いたコミュニケーションの姿が徐々に浮かび上がってくるようなステージだった。ブレイクビーツとチェロとの音量バランスなど、完全に対等なプレイヤー同士の関係性が築かれていたかどうかに若干の疑問が残る点はあったが、80歳になっても貪欲な姿勢を崩さない鈴木勲の気迫にはただただ感嘆するしかなかった。
ヒップな層からアンダーグラウンドまで日本の音楽をプレゼンテーションするような演奏が続いた前半も終了、遂に現れたのはFrostyとDaedelusによるユニット、Adventure Timeだ。Adventure Time は、LAビートシーンをDaddy Kev率いる<Low End Theory>などとともに世界中に発信し、その音楽的豊かさを支えてきたdublabの中心人物であり、DJとしても活躍するフロスティと、LAビートシーンの中核に位置し、〈Ninja Tune〉や〈Brainfeeder〉といった名門レーベルから、アブストラクト・ヒップホップの領域さえも逸脱するアルバムをリリースし続けるジャンル不問の音楽紳士、Daedelusの2人が組んだユニットである。唯一のアルバム『Dreams of Water Themes』では、洒脱な雰囲気で南米音楽からヒップホップまでミュージック・コンクレート的に調理する音楽性を見せていたその演奏は、偏執狂的な音楽への愛とクラバーとしてのテンションに支えられた、クラブミュージックの快感原則のみに支配されたようなものだった。おそらく世代的には80年代後半のレイブシーン直撃世代か、過去の音源よりも露骨にレイビーに、過剰なユーモアに満ちた演奏は、グッドトリップとバッドトリップの間を往復し続ける、KLF~The Orbの血脈に潜むアナーキズムを何百倍にも増幅したような感覚だ。子供たちの笑い声とフルートの音色、古風な宮廷音楽の優雅な雰囲気が一瞬で、重低音と阿鼻叫喚、官能に満ちたクラブミュージックに変質する瞬間の連続に、こちらはただただ笑うしかない。Animal Collectiveにもたった2人で対抗しうるのではと感じさせたほどの、異常な音楽愛に支えられた実験的ながらも強烈にキャッチーなステージは、やはりこの2人がいなければ今のdublab、ひいては音楽界全体におけるLAビートシーンの目覚ましい活躍もなかったのではないかと感じさせるほどの貫録あるものだった。
そうして、間髪入れずに最後を飾るのがDaedelusだ。トレードマークのワインレッドのジャケットを着用し、すっかり貴族的イメージをまとったDaedelusモードに入った彼が、これまたAdventure Timeの演奏でも駆使したトレードマークの機材、Monomeを手に繰り出してきたのは、何と終始BPM150~160台のトラップ、レイブ、エレクトロまみれのクラブミュージックだった。正直、最新アルバム『Drown Out』のダウン・テンポなビート感を予想していた筆者にとって、これは全くの嬉しい誤算というべきか、クラブミュージックかくあるやと言う程のエンターテイメント性を終始発揮したステージングには驚かされた。極彩色のDaedelusリミックスにかかれば全てが異様な輝きに満ち、去年、大躍進を遂げたロックバンド、Tame Imparaの「Endros Toi」といった意外な曲までもDaedelus色のアップビートなエレクトロに変貌。観客は完全に彼の掌の中だ。アップビートなトラックが続いても全く聴く側が疲れないのは、彼の巧みなサービス精神の賜物か、フロアの熱が常に良い状態でキープされ続けるように、ドープながらキャッチーなトラックを選曲するセンスは一流のDJの証だろう。アルバムで見れば『Invention』での貴族趣味的なスタイルから、『Love to Make Music to』でのディスコチックなスタイルまで、アルバム毎にコンセプチュアルな傾向が強いDaedelus、現場ではひたすら観客の心理を突いてくる演奏で意外な感じもしたが、dublabも含めてトータルに考えてみれば、彼らの精神は「いかに最高の音楽をリスナーとシェアするか」ということが肝にある。最初は営利団体として活動していたdublabが、非営利団体としてリスナーからの募金に頼った活動にシフトしたのは、彼らの利益を上手くリスナーに還元し、良質な音楽が育むコミュニティを作っていくことを意図したものだった。日本と海外における募金文化の違いに絡めて、最初のトークショーでFlostyが語ったdublabの運営の秘訣は、「募金を通じてリスナーをも巻き込んだ音楽コミュニティを作り出す」こと。LAビートシーンの豊かさは、Flying LotusやDaedelusといった有名アーティストから無名だが実力のある若手まで、音楽の制作、聴取、流通全てを含んだ「循環するサウンド」によってリスナーをも巻き込んだコミュニティが上手く形成されていることではないだろうか。良質なリスナーがプレイヤーへと変わり、良質なサウンドは新たな世代へと脈々と受け継がれ循環し続けるのだ。
全てが終わったのは深夜5時ごろのことだっただろうか。Daedelusの狂騒が過ぎ去ったフロアには、観客たちの多くが立ち去った後でも、LAのdublabスタジオからの生中継でDJたちのプレイが途切れることなく鳴り響いていた。
取材・文:宮下瑠
1992年生まれ。UNCANNY編集部員。得意分野は、洋楽・邦楽問わずアンダーグラウンドから最新インディーズまで。青山学院大学総合文化政策学部在籍。