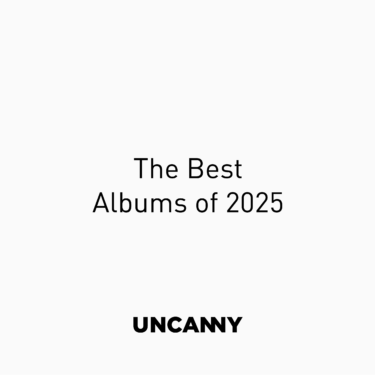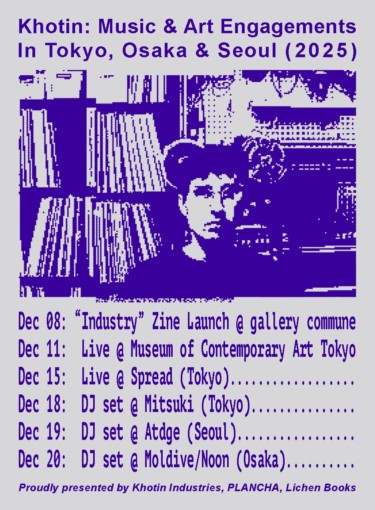- INTERVIEWSJune/06/2013
-
【Interview】Takako Minekawa & Dustin Wong – “Tropical Circle”

「遊び」とは現実の一部であり、かつ人間を超現実に導く1つの回路である。そして、人間の本質を「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人間)」という概念に集約し、遊びと文明の関係を逆転させた学者もいる程、遊びは古代から続く人間の営みに深く関わっている。なぜなら、創造性の領域において、遊び・戯れこそが創造力の源泉だからであり、文化全体を発展させる原動力になり得るからである。
Dustin Wongと嶺川貴子、彼らの出会いは全くの偶然だったが、その初めてのコラボ・アルバム『Tropical Circle』は、この出会いはある意味必然だったという思いを禁じ得なくなる作品だ。「エフェクターの魔術師」とも呼ばれ、数枚のソロ・アルバムにおいて、ギター1本でエクスペリメンタルとポップの領域を自由自在に横断しているDustin Wongと、その特徴的なウィスパーボイスを武器に、数々のアーティストと共に実験的なポップ・ミュージックを創作し、その領域を拡張してきた嶺川貴子、この2人の音楽は、キャリアの初期からその非言語的、音響的な要素を、遊び心と創造力によって拡大させることで、境界を越える力を獲得できているように感じられるからである。そこでの境は、国境であり、人間であり、言語、生活と芸術さまざまなものを含んでいる。
こんな言葉がある。
「遊びは人間がさまざまの事象の中に認めて言いあらわすことのできる性質のうち、最も高貴な二つの性質によって充たされている。リズムとハーモニーがそれである」
確かに遊びとは音楽そのものかもしれない。そして、嶺川貴子とDustin Wongの音楽はそのことを良く体現し、リスナーを超現実に導く回路になり得るものになるであろう。
2人の出会いから楽曲制作時の風景、各々の音楽観から現在の音楽に至るまで、さまざまなことを語ってもらった。
Dustin Wong
嶺川貴子
_ではまず、今作を作ることになったきっかけを教えてください。
Dustin Wong(以下D):きっかけはライブがあったからかな。
嶺川貴子(以下M):最初はFOR flowers of romanceっていうブランドでお洋服を作っている岡野さんっていう人がいて、その人のイベントに出ることになって。その時に曲を4曲くらい作って、2人で演奏したんです。
D:そこから、ライブがあってちょっと時間が空いたのかな? 2、3か月くらい。
M:11月くらいだったかな。その後にMARKっていうアーティストに誘われてUPLINKでライブをしたんですけど、その時にもう少し練習をしていたら曲が増えて。
D:そのライブは1時間くらいやらなくちゃいけなかったから、4曲じゃ済まなかった。だからライブを頼まれると、いいモチベーションになるっていうか。曲はずっと2人で作りたかったし。だからすごい簡単に曲が作れた。
_では、曲はセッション的な感じで作っていった感じでしたか?
D:そうですね。
M:出来てる曲を練習してると、その間にちょっと遊んだりして……。
D:遊ぶと曲が出来る(笑)。でもそのやり方の方が、お仕事って言うより遊びの方がいいんです。
M:自然に曲が出てくる。まあ、通り過ぎていく曲もいっぱいあったんだけど。
D:いい曲になる可能性があった曲もいっぱいあったんだけど、まあいいかっていうのも結構多い(笑)
M:楽しかったねって言って、もう一回元に戻ったり(笑)。
D:でもそういうのって大切なのかも。なんか全部リアリティにしちゃうと、息が詰まっちゃうっていうか。
_そもそもお2人が最初に出会ったのは日本ですか?
M:私が一昨年にライブを観に行って。彼の音楽は知ってたんですけど、その時初めて観て。私はただのお客さんとして行ったんですけど、共通の知り合いがそこにたまたまいて、それで挨拶出来て。
_ダスティンさんは嶺川さんのことは元々知っていました?
D:うん、音楽はずっと聴いていたし。でも来てたなんて全然知らなかった。ライブが終わって共通の知り合いの人に紹介してもらった時にすごいビックリして。「えー!ウソー!?」って(笑)。
M:私はダスティンの音楽がすごい好きだったけど、その時は活発に音楽活動はしてなかったから、自分の音楽を知ってもらえているとは思っていなくて。でも、彼に知ってるって言われてビックリしました(笑)。
_では、そこからお2人でやるようになったのは?
D:去年の冬、1月とかにまた会ったんですよ。それでその時はじゃあ音合わせしてみようってスタジオに入って、2、3回、機材とか持って入って、即興でいろいろ録ってやってみたんだけど、その時はもっとなんかフワーとしてて、曲っていうより……。
M:お互いに、私はループとマイクで声を重ねて。
D:僕は声に合わせて、ギターとか弾いたりして。
T:そしたら20分、30分くらいのすごい長い曲がいくつか出来て。
D:なんか結構ドローンみたいな感じだったから、最初はそういうドローン系になるのかなとは思ってた。でもその話をすると貴子さんが「モヤモヤし過ぎてる」っていうのをメールで返してきて。
M:まあ、でもそれは音のモヤモヤっていうより、私がどういう風にダスティンのギターの演奏に入っていけるか分からなくて、その辺でどうしたらもっと、いろいろ自分のやりたいことが出来るのか分からなくて、その辺でモヤモヤしてて……。
_では、フィーリングの部分で二人の音楽性をどうやってうまく合わせていくか、少し苦労した部分はあったと。
M:ただ自分の中ですごいこう、だんだん今の形になるまで少し時間がかかったというか……。最初は恥ずかしかったり、緊張があったりして。
D:やっぱり、リラックスした状態の方が本当にやりやすいし。
M:リラックスしたらいっぱい出てくるようになったけど。
_嶺川さんにとっては今回のアルバムは13年振りのリリースだったわけですが、それもダスティンさんと作ったこのアルバムだったら、というような気持ちになったということでしょうか?
M:本当に曲を作ってた時は、全然アルバムを出す予定とかはなにもなかったんです。ただ2人でやるということだけは目標としてはあったけど、アルバムを完成させるためというよりはライブがあって、それで曲がたくさん出来て、録音してみようってなった感じで。
_では、嶺川さんの今までのディスコグラフィーを見ていくと、共作形式が多いですが、その創作方法が好きだとか、やはり意識している部分はあったのでしょうか?
M:意識は……あんまりしてなかったんですけど(笑)。なんか出会いだったりその時のきっかけだったりで。昔はレコード会社にいて、アルバムに向かって作ったりとかしてて、しかもそれが私の名前が入ったアルバムとして、Buffalo DaughterとかDymaxionだったりと、一緒にやりたいっていうのもあってやったりしてましたけど。今回は全然最初からアルバムを出そうって感じでもなく出来たもので。だからそこはやっぱり今までとは違うものでした。
_なるほど。今回のアルバムは、ダスティンさんのアルバムとして聴いても、嶺川さんのアルバムとして聴いても違和感なく聴けるというか、トイポップともまた違う感覚の音楽だと思ったんですが、それに関してはあまり意識しなくてもポンポン出来ていった感じでしたか?
D:うん、あまり狙いはなかった。
M:なにも、こういう風にとかは全く(笑)。
_お2人ともそれぞれ作曲されると思いますが、その時々の方法と今回の方法では違いはありましたか?
D:1人でやるより楽しかった(笑)。1人で曲を作ってても、それを完成させた瞬間に誰かに伝えることが出来ないじゃないですか。「出来た!」って1人で言っても、その後にショボーンってなっちゃうし。でも誰かいたら「今の良かったじゃん!」ってすぐ反応が返ってくるところが嬉しい。
M:笑って踊りながら作ったりとか(笑)。結構楽しかった。
D:遊びでした(笑)。
_ダスティンさんの場合、緻密なギターループを駆使した楽曲が多い訳ですが、その時は楽曲の構造から作るのか、絵画的なイメージから作るのか、どっちの感じが近いですか?
D:イメージはないけど、最初のフレーズは想像して始まる場合が多いですね。でもそこから何が出来るかは分からないし、別にゴールは作らないタイプ。何となくはあるけど、細かい何かは何もないから、楽しくてやったことのないやつが出来たらいいなって。やってれば何かは出来てくるけど。
_つまり、やりながらどんどん膨らませていく作り方というか……?
D:でも何だろう、なんか紙があって、最初の線を書くのが一番難しくて。最初の線が書けたらそこからはスラスラ、模様とか色とかついていく感じ。
_では割と絵を描く感覚に近い?
D:絵だけど、もっと抽象的な絵なのかな?もっと感情的なものもあるけど。
_ダスティンさんはボルチモアでは美大に通い、それ以前はアニメーションの勉強もされていたそうですが、そもそも音楽と絵画はどちらを先に始めましたか?
D:絵ですね。
_では音楽を作る上でも、他の芸術作品に刺激を受けて曲を作ることとかはありますか?
D:うん、もちろん。
_自分の中ではそこに壁はない感じでしょうか?
D:壁は無い方がいいと思う。フルクサスのアラン・カプローの本で、「生活とアートの壁をぼかす」って読んだことがあるんだけど。僕が美大にいた時の先生はそれを真剣に教えてくれたから、それには結構影響を受けてると思う。
_では、嶺川さんも自分で作曲する時は割とフィーリング重視なタイプですか?
M:何か音みたいなものが1つ出来たところから膨らましていく感じは多分、似ているし、セッティングは普段やる時とはちょっと違うんですけど。でもそれは初めてのやり方というよりは割と近い感じだったから、自然に出来たし、私も1人の時より広がるからすごく楽しい感じはしました。
D:セッティングはすごく考えたよね。
M:それはすごく実験でした
D:曲を作ることについてはあんまり考えないで、一番やりやすく曲を作れる環境を一番考えました。やっぱりゲームを作ってる感覚と同じかも。2人でどうやってこう、一番楽しめる環境を作るかっていうのは。だからそうね……カリキュラムっていうか……なぜか教育のことを考え始めてるんだけど。
M:今?
D:いろんな学校のやり方。私立とか公立とか、すごい自由な学校から、すごい規制された学校まで。クラスのない学校とかあるじゃないですか。それだとノイズとフリージャズになっちゃう。
M:だから何も制限がない状態で2人でやるとノイズとかドローンっぽいものになっちゃうんだよね。お互いに制限っていうとちょっと窮屈な感じになっちゃうけど。
D:少しはルールはあるんだよね、やっぱり。
M:お互いになんか……暗黙の。
_暗黙のルールのような?
M:その辺はあんまり、深く考えなくても説明しなくても、私はとても楽でした。
D:僕も楽だったよ。
_今回のアルバムはアナログチックな音の暖かみとかニュアンスに対して、すごく音質的に意識してる感じがしたのですが、そこら辺へのこだわりはありましたか?
D:こだわりは……なかったよ(笑)。なんか、ちゃんといい音で録れればいいなっていうのはあったけど、録音した環境があれだったからだと思う。
M:曲を作ったりしてる環境も気持ちのいい部屋だったりしたから、いろんなものが影響していて、その時のいろんなものがいい形に影響していただけで。
D:マイクも本当に普通のSM-57っていう1万円弱のマイクを使ったんだけど、それは本当に普通のマイクで。環境がいい音楽を作ってくれたんじゃないかな。ミキシングはすごい頑張ったけど、こういう音っていうのは別に。こういう音が録れたからこの音でっていう。
M:その録れた音を一番いい形にしてくれたんじゃないかな。
D:逆にそれしか出来ないから。
_では今回は全部宅録でライブの時と同じ機材を使って録音を?
D:生で一発録りしたんじゃなくて、1つ1つレイヤーにしてトラック化していったスタイルだったけど。
M:まあ、それも完成していた曲をちょっと丁寧に重ねていくような感じで。
D:普通のステレオのスピーカーから出して、それを聴きながら。
_では自分のソロ・アルバムのときの方法もそういう感じですか?
D:自分のアルバムでは結構いろいろ実験してますね。次に出すアルバムで今年中に出すのもあるんだけど、それも含めた3つは全部違う風に録音してて。同じ風にやっちゃうと、こっちも何か退屈だし。最初のアルバムは1つずつ全部トラック化して、それでミキシングしたんだけど、ミキシングに時間がかかってすごく難しかった。それで次のアルバムは全部生演奏で録音しようってなって、それも実はすごい早く録音出来たけど、ミキシングがすごい難しくて。元がモノラルで録ってて音の広がりが点だったから、それを広げさせるのがすごい難しかったし、アンプも直でやったから。それで、一番新しいのは直だったけど、全部バラバラにして。でも全部時間がかかっちゃう(笑)。だから難しいなと思う。
M:でもいいものにはなったと思う。
D:宅録の方がお金と時間とプレッシャーを気にしなくていいからいいですね。スタジオの方がいい音で録れるのかもしれないけど、何かスタジオって音が抗菌されてる感じがある。宅録には少しざらつき、質感がある。
_Ecstatic SunshineからPonytail、そしてソロへという活動遍歴の中で、個人的には常にダスティンさんの核にはポップなものがあって、それが最近の作品ではどんどん分かりやすい表現に向かっているように感じられたのですが、どう思いますか?
D:実験的な音楽も好きだけど、ポップも好きだし、好みですね。でもポップのいいところって優しさがあるところだと思う。音楽を全然知らなくても聴けるし、それをバカって言う人もいると思うけど、そんなの関係ないと思う。
_確かにメロディだけだったら国も言語も関係なく理解できますね。
D:鼻歌がそうだし。昔、ボルチモアに住んでたんだけど、フリージャズとノイズの人たちが多い町で、その人たちと話すると、よく「何でメロディまだ使ってるの?」って言われた。「何でそういう風に演奏するの?」って。メロディはもう死んでる、すべてのメロディはもう演奏されたって。僕はそうじゃない。だってもうそんなこと言ったら何も出来なくなっちゃうから。
M:私も同じメロディでも誰が演奏するか、誰が歌うかで全然違うし、エッセンスが入るし、同じものにはならないと思う。
_そうですよね。この前Mark McGuireさんと共演していましたけど、MarkさんもEmeraldsを脱退してからそういう路線に行こうとしてる風に聴こえるというか、お2人の間で共通しているものとかについて、話し合うことはありますか?
D:Markの場合は、本領発揮してるみたいです。彼は今、全然押さえないで全部出し切る感じで、音楽作ってるみたいで。だから聴いててちょっと恥ずかしくなっちゃう瞬間もあるけど、瞬間瞬間に全部出し切る感じで、情熱があって。あと今彼はLAで映画音楽を作ってるみたいで、それの影響もあると思う。Emeraldsはエクスペリメンタルって言われてるけど、そういう部分から、メインストリームなところへ重なっていこうとしてるのが今の彼だと思う。それがすごい面白い。でも勘違いされる場合もあるかもしれないけどね、ずっとエクスペリメンタルやってて、そこから歌とかリズムとかニューエイジっぽい音だったりをやると。でもそこを理解してくれればすごい面白いものだと思う。
_なるほど。ところで、ダスティンさんは思春期を日本で過ごされたんですよね?
D:18歳までいました。
_今回の作品もそうですが、個人的にはダスティンさんの音楽からはオリエンタルな響きというか、どこか懐かしいものを感じることがあります。自分自身の血や思春期の経験が影響している部分はあると思いますか?
D:やっぱり自然に魅かれる音色とかあるんじゃないのかな。だからベンチャーズがすごい流行ったのかも、日本で。サーフ・ミュージックのマイナー・ペンタトニックな感じとかオリエンタルのような気がする。
_確かにベンチャーズは海外よりも日本で人気があるらしいという話は聞いたことがあります。やっぱり国は違っても共通して通じる響きはあるのかもしれませんね。
D:そういう何か、メロディのエッセンスみたいなものはあるのかも。
M:私は日本で暮らしている日本人だけど、ダスティンの作品とかメロディを聴いているとすごくハッとすることが多くて。日本での生活もあって、アメリカでも暮らしてたから、自分の中にあるそこから出てくるものが、日本人以上にすごく深いのかも。だからきっとそれで聴いた人は何か分からないけどワッてなるのかな。私自身もそうだったし、何か感じるから。
D:ありがとう(笑)。アジアの、ペンタトニックとかああいう音を弾いたり聴いたりするとすごく気持ちいいよね。
M:ミャンマーの人の、民謡じゃないけどそういうのを一緒に聴いたりしてね。
D:5つの音なのに、1つ1つの国によって違うリズムとか重なり方があって、すごくそれは興味深いですね。
_今回のアルバムには水の音とかトイポップっぽいおもちゃ楽器の要素とか、『Cloudy Cloud Calculator』的な要素が入っていましたが、嶺川さんの曲のそういう部分にはやはり魅かれますか?
D:『Cloudy Cloud Calculator』は好きですね。例えばBBC RadiophonicとかRaymond Scottの作品とか、そういう音を使ってる人たちの作品には、ノスタルジックじゃないけど懐かしい部分があるし、なんかエッセンス的なものを感じるのかな。そういう音は普通の楽器で出す音じゃなくて、プロフェッショナル、アカデミックな感じがしないから、それを通り越してエッセンスに近づけられる気がする。貴子さんの音楽を聴くとそういう人たちを思い出しますね。テクニックじゃなくてイマジネーションが伝わるから、その方がエッセンスに近づいてる感じがするの、かな?
M:2人でやった時はサンプラーにいろんな音を入れて、水の音を太鼓みたいにして使ったりしたのはありました。
_お2人は最近の音楽は細かくチェックするタイプですか?
D:あんまり。好きなものは好きだけど。James Ferraroとかは面白いと思うし。友達なんだけどCo Laとか。
M:面白い。
D:シカゴ・フットワークとかも大好き。TraxmanとかRP Boo、DJ Rashedとか……。
_音楽的に、メロディだけじゃなくてリズム面でも実験的で意識されてる部分を感じました。
D:やっぱりSteve Reichとか、Philip Glassとかのリズムは好きだったし。でも一番勉強になったのは、ボルチモアでTerry Rileyの「In C」を演奏した時に、初めて楽譜を使って演奏した時でした。でもそんなに昔じゃない、2、3年前のことなんだけど(笑)。僕は全部記憶をベースにしてて、楽譜とか読めないんです。でもそこで初めて楽譜を見て演奏して、何十個かのフレーズがあってそれが全部重なると、ポリリズムとかになって。それがすごく勉強になって、そしたらもう、そこからどんどんドアが開いていった感覚でした。
_では本当に現代音楽からポップなものやノイズ、ドローンまで、全てがジャンルなど関係なく自分の中で並列に存在していると。最近のミュージシャンは本当にジャンル関係なくそれぞれの表現を追求している人が多いと思いますが、やはりそういう事に関して共通理解のようなものはあるのでしょうか?
D:なんか最近ジャンル差別って無くなってきたよね。僕はメタルだからとかそういうの、あんましないもん。それはインターネットのおかげなのかな? Tumblrとか見ててもそう思う、全部繋がってるし。いろんな時代のものが1つのページで1つのものとして見れるから。
_特にYouTubeとか本当にそうですよね。
D:だからWEBなんだよね、本当に。
_やはり物心ついた時から、そういうWEBが身近にあって、自然とそういう聴き方が身についていたということですよね。
D:関連動画とか横に出てくるじゃないですか、YouTubeで。例えばOASISの動画観てて、横に植木等の動画とか出てきたりすると、何だこれ?って(笑)。
M:それはあるのかな?
D:ないかもしれないけど(笑)。
_ではこの前のリリースパーティーでは新曲も演奏していましたが、それもまた作品を発表するとかとは関係なく、これからもなんとなく2人で活動していくという感覚でしょうか?
D:でも、曲は作っちゃったから、次はEP出したりとかもいいんじゃない?とは軽く話したりしてたけど。やっぱり人に聴いてもらいたいし。
_では嶺川さんも海外にはファンの方が多いと思いますが、海外でライブをやったりとかするご予定は?
D:出来たらしたいですねー。今僕もヨーロッパとかアメリカでツアーとかするんだけど、ちょっと探ってみようと思っています。
■嶺川貴子 & DUSTIN WONG『TOROPICAL CIRCLE』
発売記念インストア・ミニ・ライヴ&サイン会
開催日時: 2013年 6月9日(日)16:00 start
場所: タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
内容: ミニライヴ・サイン会
参加方法: 観覧はフリーです
(イベント参加券をお持ちのお客様を優先でご案内させていただきます)
*詳しくはこちら
■嶺川貴子ソロミニLIVE in Lamp harajuku
2013年6月16日(日)
18:45開場 19:00開演
前売り2000円/当日2500円 (定員40名)
アヒルストア提供のワンドリンク付き
Lamp harajuku店頭にて発売中
[お問い合わせ先]
Lamp harajuku:150-0001 東京都渋谷区神宮前4-28-15
TEL:03-5411-1230(営業時間12:00~19:30)
http://www.lamp-harajuku.com/
*詳しくはこちら
取材:宮下瑠
1992年生まれ。UNCANNY編集部員。得意分野は、洋楽・邦楽問わずアンダーグラウンドから最新インディーズまで。青山学院大学総合文化政策学部在籍。

Artist: Takako Minekawa & Dustin Wong
Title: Toropical Circle
Label: Plancha
Number: ARTPL-037
Release date: May 15, 2013
Price: 2,310yen(tax in)
01 Party on a Floating Cake
02 Windy Prism Room
03 Circle has Begun (yorokobi humming)
04 Two Acorns’ dreams Growing as One
05 I Want to be with You
06 Swimming Between Parallel Times
07 Bell Tree Dancers
08 Enneagram Journey
09 New Circle was Begun
10 Story of Roots and Hands
11 Solar Glory
12 Electric Weave
13 Mirror Underwater in a Magic Lantern