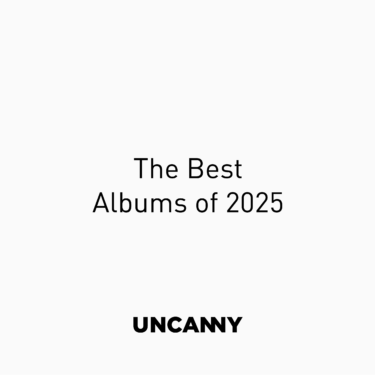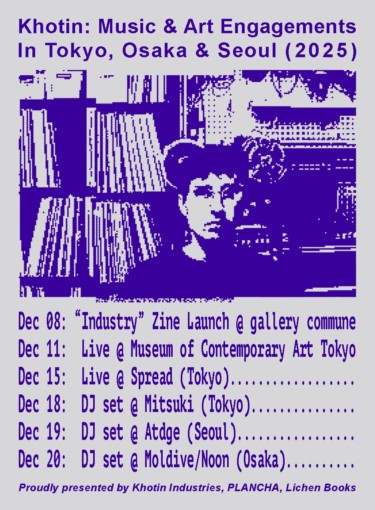- INTERVIEWSMarch/15/2016
-
[Interview]The fin. – “Through The Deep” (Part.1)

神戸出身のインディ・バンドThe fin.が、1st Album『Days With Uncertainly』のリリースから1年3ヶ月ぶりとなる新作EP『Through The Deep』を3月16日にリリースする。
2014年3月に1st EPとなる『Glowing Red On The Shore』をリリース以降、日本に留まらず世界各国での精力的なライブ活動を行ってきたThe fin.。彼らは、1st Albumで“不確実性”というものを肯定し、発表予定だという2nd Albumではその変化の結果の到達点を示すと語る。今回のインタビューでは、踠きながらも彼らが進む方向を模索した“変化の過程”という大きな一瞬について、過去と未来という変化の両端を見据えながら語ってもらった。
The fin.
Yuto Uchino
Ryosuke Odagaki
Takayasu Taguchi
Kaoru Nakazawa
“ノンバーバルな所をもっとサウンドで表現していく”
__3月16日にNew EP『Through The Deep』を発売されるということで、おめでとうございます。最初にEPを完成させた今の率直なお気持ちをお聞かせください。
Yuto(以後Y):えっと……、EP自体を出すつもりがあんまりなくてね。2015年は結構海外での活動が多くて、そこでの兼ね合いで急にEPを出そうってなったんです。曲自体はいっぱい作っていたので。ほぼ1年前くらいに作った曲を中心に、2nd Albumには入らないようなアウトテイク的な感じで作りました。だから結構バラエティに富んでるかも。EPを完成させたというよりは、2nd Albumに向かって進んでいっているっていう気持ちの方が強いから、あんまり「完成させた」っていう気持ちは正直あんまりないんですよね。
一同:(笑)。
__なるほど。では、このタイミングでEPを発売したのは、海外での活動も踏まえてこのタイミングで日本での音源を出しておこう、という意味合いなのでしょうか。
Y:そうですね、これを出すのは日本とアジアなんですけど、これは一応日本で出す音源としてのEPですね。
__1st Albumをリリースしてから1年3ヶ月が経ちましたが、その中で特に海外公演を含め、何本ものライブを行ってきて得たもの、進化した部分は何だったのでしょうか。
Y:何やろう……、海外でやるライブっていうのがある種自分たちにとってのライブの基準になったところがあって。最初日本であまりライブをやってなかったっていうのも、正直ライブに対する印象があんまり良くなかったからなんですね。それは多分音楽性もあるんですけど。なんかこう、ライブが終わった後も、良かったよって皆言ってはくれるけど、自分たちの中でもやっとするものがあって。でも海外にいったらそれが無かったんですよね。すごく自然に出来た部分があって。そこでちゃんとバンドとしてのライブっていうものを目指せるようになったんですよね、自分の中でも。
今まで日本だけでライブをしていたときは、ライブに対して今ひとつ熱意を置けていなかったというところはあるんですけど、海外に行くとライブに対してエネルギーを持っていけるんですよね。何やろう、生で作っていく感覚が海外の方が強いというか。そういう感覚があったから、良い意味で演奏に対してもシビアになれたし、プロフェッショナルになろうっていう気持ちも芽生えたし。どちらかというと、ネットとかで音楽やってるとあんまりフィジカルじゃなくて、頭とかが重要になるんですよ。でもツアーとかやると、フィジカルやバンドのリアルな部分がすごく大事になるんだなっていうのを感じたから、そこに気付けたのは海外に行って良かった部分かな。
__1st Albumはボーカルの声もメロディもはっきりしていたり、楽器のサウンドも動きがあったり、アコースティックギターの暖かみがあったり、チルウェイヴやシンセポップの要素を持ちながら、バンドを確かに感じるサウンドといったイメージがありました。でも、今作のEPは、まずエレクトロニカ色が強くなったというか、音色として無機質な電子音楽の要素が増えたようにも感じました。
演奏に関しても一人ひとりがメロディやリズムで主張するというより、良い意味でその楽器の主張や個性を抑えて、4人の音が重なることで初めて音楽やそのグルーヴを生むことに重視したように感じたというか。例えば曲を聞くときってまず歌を聞き入ってしまうと思うんですけど、今作ではボーカルに結構リバーブをかけて、メロディもシンプルで、歌というよりもこの音楽を構成する楽器としての声であるように感じたんです。音数に対する引き算の考え方もそこから生まれるグルーヴを大事にする姿勢も前からあったと思うんですけど、それが更に強くなったなと感じて。音数自体も更に削って一層タイトになったというか。そういったサウンドに関する変化も海外で受けた影響からですか?
Y:正直、僕日本の中には音楽の種類ってあんまりないと思ってて。世界には沢山の音楽があるけど、多分日本人が聞く音楽ってかなり限られてると思うんですよね。ざっくりいうと歌謡曲。でもそれが悪いって言ってるんじゃなくて、歌謡曲も歌謡曲として進化してるし、今聞いたらすごいなとも思うし。でもそれしかないっていうのが、価値観を狭めてる一つのポイントなのかなって思ってて。なんかこう、もっといっぱい音楽やその表現方法がある中で、日本にいてもどこにいても、どんな音楽表現を自由にしてもいいんじゃないかっていう認識は多分前よりも強くなりましたね。それがサウンドに出てるかもしれないし。
あと俺らって、多分サウンドとかを描写的に使ってるんですよね。アレンジとして使っているというよりかは、表現としてサウンドを使っていて。そういうのが多分日本には分かりにくいんじゃないかなって思いますね。これは自分の感覚なんですけど、例えば小学生の時とかに美術館とか行っても正直全然分からないじゃないですか。ただの絵、みたいな。でも今見たらその絵が表現しているものが伝わってきたりする。もっとこう、言語的じゃない何かというか、言語的じゃないものの情報の力っていうのを俺は信じてるんですよね。それが俺にとってはサウンドやし、声の表情やったりしてて。海外に行くとそれを強く感じるというか。
日本にいると、言葉の力って結構すごいんですよね。それは日本の良い所の1つやとも思うけど。例えばバラエティ番組を見てても、言葉全部に字幕がつくんですよね。全部言ってるのに言葉がついてる。その字に色がついていたり、ある部分が大きくなっていたり、読み手の受け取る言葉のポイントっていうのが作り手に全部コントロールされてしまう。で、ここで笑うんだよっていうのも作られてるから、皆同じ所で笑って、同じ所を面白いと感じてその番組が終わっていくみたいな。俺もその中で育ってきたから今まではそのおかしさに気付かなったんですよね。
でもヨーロッパから来た友達とかと一緒にいると、「なんで全部言ってることをわざわざ全部書くの? 聞けば良いじゃん」っていうのを結構皆言うんですよね。で、実際に自分が海外に行って感じるのが、やっぱり耳の情報量が多い。なんかこう、目に頼り過ぎていないというか。例えば読む文字と聞く文字って全然違うじゃないですか。話して入ってくる文字と書いて出せる文字と。それのバランス感覚が日本とは違うのかなって。それが音楽的な面では強くなってきてるのかなという気はします。全体的な調和を目指して、歌詞、サウンド、ビートに頼りすぎない姿勢というか。そこのバランス感覚が、色んな国に行って色んな人と話していく中で自然と出てきたというか。今までずっと日本にいたからそれに気付かなかったんですよね、そのアンバランスさが自分の中で当たり前やったから。でもそれは意外とそうでもないんやなって。そのノンバーバルな所をもっとサウンドとかで表現していくっていうのは音楽やってる身として大事なんかなって思いますね。
Taguchi(以下T):ちょっと話し変わっちゃうけど、俺の解釈としては、1st Albumよりもエレクトロニカ色が強くなったサウンド面の変化はYutoが海外で受けたインスピレーションが大きかったっていうのもあるけど、単純に方法論として、今回のEPは割ときっちり打ち込みをYutoが使ってきて、作ったデモを各々が聞いて、そのイメージで各々がアプローチをしていくっていう方法が出てきたのもあると思う。1st Albumはバンドで音を出してそのアンサンブルから生まれたものが結果として残ったけど、今回打ち込みを使ってみたら、やっぱりサウンドの選択肢が広がったんですよ。そこにある可能性を今回のThe fin.では使いたくて、俺はそういうイメージでやってましたね。それが結果として、エレクトロニカ色が強くなったっていう印象かなって思う。
Y:やし、結構走りよね、この曲は。俺がデモでアレンジするパーセンテージが前よりも高くなって。1st albumを作ってる途中、終わり位からかな。やっぱり自分もバンドに対する不自由さは感じてて。何だろう、ありきたりなギターロックしか生まれない、みたいなその価値観や不自由さっていうか。それを自分でぶち破りたかったっていうのと、もうちょっと自分の世界の中で飛び回りたかったというか。
自分の音楽の中で自分をもっと自由に走り回らせたかった。その中で、デモを自分で完成形に近付けるっていう作業があって。それが自分の中で有効な手段の一つやったんですよね。バンドの初期はデモを作っても、単純なリズムとベースに、アレンジされた自分のシンセと書いた歌を乗せて皆で聞いて、スタジオでああするこうするって話しながら作る方法だったんですね。でもそことはまた違う作り方をしてみたというか。さっきも言ったように、自分の想像力を限界まで伸ばして、やれる所までやってみてからバンドに投げるっていう作り方の、本当に走りの方やったんですよね。だから曲もバラエティに富んでるし、結構自由に作れたのは大きくて。
T:普通にやっぱそう作ると、しっかり練れるんですよね。例えば単純に模型を作るとして、一つひとつ部品を選んでからひとつの模型を作ることも出来るけど、最初に読む説明書みたいな感じで、こうしたらこうなりますよっていうのがある程度掴めている状態で作っていくイメージだったかな、俺は。だから良い意味でリズムに対するアプローチも強くなったし、悪い意味って言ったらおかしいけど、バンドサウンドとして抑えられた部分もあるし。
Y:そうそう。良い意味も悪い意味もあって。ある意味音数が減ったっていう印象も、多分そこが出来てたから。多分俺のイメージがそこにしっかり乗ってたから、変な不純物が入ることも無く、すごく分かりやすい状態で曲に向かっていけたというか。前の作り方も良い所はあったけど、悪い点を挙げるならば、俺が出してるところが中途半端やったから、色んな解釈が混ざってゴチャッとして。そこから生まれる良さも勿論あるんやけど、そこから生まれる拙さみたいなものもあって。でもなんかこう、それはそれで、これはこれで良いし、みたいな。
T:色んな方法がある中で、今はこっちを突き詰めた方が良い、っていうモードにThe fin.が入ってる。
__The fin.にも同じ印象を持ったんですけど、引き算がうまい音楽ってそこに表現としての音や受け手の想像が生きる空間というか余地があるじゃないですか。さっき日本の価値観の枠組みやそのバランスを自分の価値観や音楽の中で壊したいと仰ってましたが、多分日本の音楽っていうものにも枠組みがあるんですよね。それこそアレンジとしてのサウンドが多い様な気がします。だからさっきのサウンドの変化についてのお話で、表現としてサウンドを使っているという言葉がすごくしっくりきたんです。
音数が少ないというよりも、音を生かす為の空間が表現としてそこにちゃんと存在している、そんなイメージをバンドで作るってすごく難しいんじゃないかと思うんです。それはきっとYutoさんが持つイメージで曲を完成形にまでした状態で共有したからだと思うんですけど、そこの共有というのはすぐに出来たものだったんですか?
Y:そこにはさっきも言ったように、言語はなくて。デモで伝えることが出来るから、そこも音楽的コミュニケーションが出来てる気はするし、それは良いことなのかなって思います。変に言葉でがやがや言うよりも、聞いてって感じやから。
T:話すと特に長いもんね(笑)。ここはこうでああして欲しいこうして欲しいって。
Y:そうそう。言うならば、俺がデモでほんまに喋りまくって、それを皆が聞いてくれてるって感じ。
“変化がどうっていうよりは、The fin.が良くなるために自分は何が出来るのか”
__バンドの音楽を作る方法って、仮デモを聞いて各パートが自分でアレンジをして、そこからのバンドのアンサンブルから作るものと、バンドの中に1人ブレインがいて、そこに皆が合わせていくっていう方法があると思うんですけど、多分前者だった方針が少しずつ後者に寄っていったということですよね。その時楽器隊の皆さんはどう思われましたか?
T:俺としては、純粋に音楽が良ければ良いっていう考え方やから、そもそもの根本が。だからその方向でいくのにも違和感はなかったし、それでThe fin.が音楽的に成長していけるなら良かったし。演奏に関したら、このバンドでベース弾いてるのは自分やし、勿論悪くしたら駄目やし。デモを聞いて、そこから自分がもっと良くしようっていうアプローチを特に心がけてたし、そういう解釈でやってたかな。これで分かるかな(笑)。
__よく分かります。
Y:だからあれよね、そのプレイ面での表現っていうのもより練れるようになったし。なんやろうな……、やっぱり音楽的コミュニケーションは増えたのかな、その情報量が。
T:リズムとか手癖とかっていうのはやっぱりその人が出ると思うから。だからそこはもっと自分が頑張っていかなあかんなと思うし。任せっきりにしたりデモ通りじゃなくて、自分のプレイをもっと良くして、それでThe fin.を良くしていきたいっていうアプローチの仕方やったな。伝わった(笑)?
__伝わりました、ありがとうございます。では、Ryosukeさんはいかがですか?
Ryosuke(以下R):多分さっきもあったんですけど、バンドのモードとかって変わっていくから、1st Albumを出した時のThe fin.はもういないし、逆に言えばその時とは違うThe fin.がここにいて。それは多分作曲に関しても何に関してもそうで。でも、さっき言いはったみたいに、ブレインがいるからこうしなきゃいけないとかじゃなくて、その中で僕がやることっていうのがあって。言われた通りに弾く為に僕はここにいるわけじゃないから。
だからそれはバンドが変わっていくと同時に自分も在り方を考えないといけないし、結果的には今その変化途中の曲がこのEPに入ってて。だから今の形も、こうせなあかん、みたいな感じには捉えてなくて、じゃあここから自分には何が出来るのかってことを考えてますね。確かにバンドのモードは変わりつつあるし、でもそれが結果的に良いか悪いかなんて誰にも分からないじゃないですか。でも変わっていくことに価値はあるし、バンドには。同じままやったら、息が続かないし。だから多分2nd Albumが出来たらその時は今と違うThe fin.がいると思うし、自分はそれに向かって進んでいけば良いのかなって思ってますね。
__ありがとうございます。ではNakazawaさんはいかがですか?
Nakazawa(以下N):そうですね……、俺は、多分ドラムって基本的な所はデモからあんまり変わらないと思うんですよ。それが変わったら全然違う曲になるし。だから例え作り方が変わっても、デモを聞いて、そこにあるものを出来るだけ忠実に再現して、っていう感じになってくると思うんですね。だから作り方が変わっていっているのは思うんですけど、自分がその中でやることとしてはそんなに変わらないんですよね。
Y:Nakazawaが多分一番変わってないよな。
__バンドって1人じゃ出来ないわけじゃないですか。作曲者の方はその曲のイメージがあって作っているわけだから、そのイメージと違うことをやるわけにはいかないし、かといって他のメンバーの皆さんも、今まで楽器をやってきて、自分のルーツとなる音楽がそれぞれあって、練習してきた手癖みたいなものがあって、演奏したいものがあると思うし。そこを重ねるのが多分一番難しいんじゃないかと思うんです。「俺はこういう方が格好良いと思うのに」みたいに、その曲や演奏に対して感じることは皆違って当たり前なんじゃないかと思って。だから作曲方法やサウンドが変わっていった時に皆さんはその変化についてどう捉えていたのかをお聞きしました。
R:多分単純に、皆元々「The fin.を良くしよう」って思ってやってるから。それが強いバンドなんかなって思ってて、僕は。
T:そう。The fin.としてそれが良いならそれで良いんちゃうっていう(笑)。
R:だからそこの変化がどうっていうよりは……、なんていうかな、The fin.が良くなるために自分は何が出来るのかっていうのが各々違うっていう感じですね。
T:まあ、チームやしね、俺達(笑)。
__そのイメージはすごくありますね。やっぱり音源を聞かせていただいて、各々がプレイヤーとしてバンド内で主張しながら演奏していると言うよりは、The fin.の音楽を作る1人として各々が担う役割という意味での演奏といったイメージがあったんです。元々皆さん幼馴染ということもあって、きっと音楽的コミュニケーションもしやすかったのだろうし、バンドの方向性の共有もしっかり出来ていたからこその在り方なんだろうなと思います。
U:そうですね、それはあると思います。
“あらゆる変化を受け止める中で、進むべき方向が見えてきた”
__ありがとうございます。では次に今作『Through The Deep』というタイトルやアートワークを含めて今作におけるイメージやテーマについてお伺いしたいと思います。まずこのアーティスト写真やアートワークのイメージは自分たちで持っていたものなんですか?
Y:これはフォトグラファーの方にお願いしました。ライブもよく来てくれるし音源もちゃんと聞いてきれていて、多分表現者として、The fin.のことを分かってくれてるんですよね。だから今回のイメージにすごく合ってるし。まあ撮った時めっちゃ寒くて救急車で運ばれたやつもおるし、ほんまに大変だったんですけど。
一同:(笑)
__お疲れ様でした(笑)。本当に素敵な写真だと思います。では次に、『Through The Deep』というタイトルについてお願いします。
Y:前作の『Days With Uncertainly』も、結構暗いタイトルみたいな印象でとられることが多くて、まあこれも暗いととれば暗いととれるんですけど、全然そんなことはなくて。このアーティスト写真とかすごく示していると思うんですけど、どこかじっと見ている様な感じなんですよね。例えば暗い場所からぽつりと浮かび上がる光をじっと見つめているような。
俺、『The Great Gatsby』が好きなんですけど、あれって全体的に見たら悲しいというか、惨さがあるというか……。まあ楽しい話ではないやんか、めっちゃ簡単に言えば。でも俺がすごく惹かれるところは、好きな女の子の住む豪邸の対岸にわざわざギャッツビーも豪邸を買って、その子に知られる為にパーティを開きまくってさ、それなのに1人で海の向こうにある灯台の光をじっと見ているところ。ギャッツビーってそういう人で。生まれた時には貧乏でお金も何も持っていなくて、それでもいつも光を見失わんかった。対岸にある灯台の光を見つめるって、ギャッツビーの生き方の比喩であって、彼はその光を、どんな手を使ってでも、って言ったらおかしいけど、手に入れようとした。俺はそこに勇気をもらえたんですよね。そんな気持ちって多くの人はあるんちゃうかなって思うんですよ、『The Great Gatsby』を読んで。で、俺もそういう思いが強くて。なんだろう、だから『Through The Deep』はそういう虫の走光性というか、光に向かっていく感じと言うか。もがいていたり、色々あるけど、でも前に進もうとしているっていう。そんなイメージですね。
__なるほど。1st Albumのタイトルもネガティブなイメージで捉えられやすいけれど、その不確実性を前提として変わっていく自分たちを肯定的に受け止めるっていうイメージは今のThe fin.の在り方としても存在しているんだろうなと思います。バンドの根幹にある変わらない部分というものが確固としてあって、その上で変化をし続ける姿勢というか。では、タイトルにあるイメージの方向性としてはそこまで変わっていないということですか?
Y:そうですね。でもなんか前よりも一途になったというか、段々自分の中でそれがピュアになってきたというか。
__1st Albumであらゆる変化を受け止める中で、進むべき方向が見えてきたというか。
Y:そうですね。1st Albumを出したときはまだ本当に散らかっていたというか。まず、散らかっているというその現状を受け止めたっていう段階やったんですよ。そこから今作で、もう一度自分を発見出来たというか。でもそこにちゃんと辿り着くのは多分このEPよりも2nd Albumなんですよね、自分の中で。だからね、正直EPで語れって言われてもね、これは一過性のものだからね(笑)。ほんまに通り道みたいなもんやからね。
__現段階でのThe fin.はこれです、っていう感じですよね。
Y:そう。だから例えば、今日東京から大阪に新幹線で行くねんって話をした時に、じゃあ名古屋どうやったって聞かれても分からへんよっていう(笑)。だから難しい。この時どうやったっけかなって思っても、うーんってなってしまって。2nd Albumの感じはすごく分かるんやけどな。
__その2nd Albumまでの過程としての、変化途中である現段階での報告みたいな感じですよね。
Y:そうそう。大変化の兆し、みたいな。
__やっと見るべき方向が分かってきたというか。
Y:そう、それが特にこの『Through The Deep』に表れてますね。それが固まってきたときの曲かな。確か7月とかに作った曲で、割と新しい曲なんですけど。
(Part.2へつづく)

■リリース情報
Artist: The fin.
Title: Through The Deep
Release date: 2016年3月16日
Price: ¥1,500(税別)
1.White Breath
2.Divers
3.Through The Deep
4.Heat
5.Anchorless Ship
6.Night Time (Petite Noir Remix)
■ライブ情報
Through The Deep Tour
2016年4月01日(金) 心斎橋 Music Club JANUS
OPEN 18:30 / START 19:00
2016年4月02日(土) 名古屋 CLUB UPSET
OPEN 18:30 / START 19:00
2016年4月09日(土) 渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
2016年6月10日(金) 台北 THE WALL
OPEN 19:00 / START 20:00
2016年6月16日(木) 仙台 CLUB SHAFT
OPEN 18:30 / START 19:00
2016年6月21日(火) 広島 4.14
OPEN 18:30 / START 19:00
2016年6月22日(水) 福岡 The Voodoo Lounge
OPEN 18:30 / START 19:00
チケット
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
※台湾公演 ADV NT.1100 / DOOR NT.1300
*公開時、アーティスト名の表記に一部誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。(3/15 22:02、訂正済)
1994年生まれ。UNCANNY編集部員。青山学院大学総合文化政策学部在籍、音楽藝術研究部に所属。
![[Interview]The fin. – “Through The Deep” (Part.1)|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)