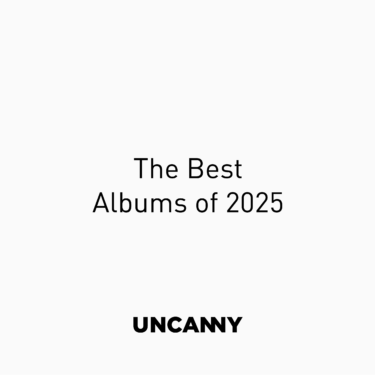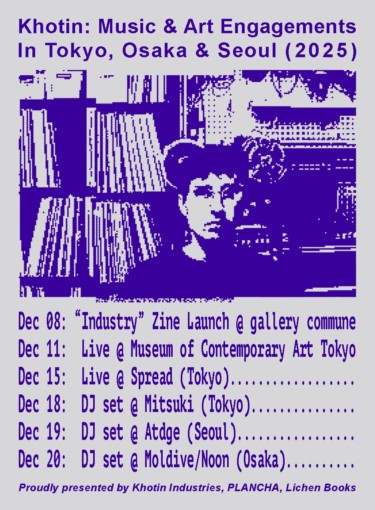- REVIEWSNovember/16/2012
-
【Review】Flying Lotus | Until The Quiet Comes
2006年、J Dillaの遺作となった傑作インストゥルメンタル・アルバム『Donuts』がリリースされた。その同じ年に、Flying Lotusは、ファースト・アルバム『1983』をリリースしている。J DillaやMadlibのビートに影響を受けつつ、ヒップホップの枠の中で新たな可能性を生み出したのがその『1983』だった。そして2008年、『Los Angeles』のリリースによってその可能性は予想を遥かに上回るスケールで開花し、その勢いをもって自身が主宰するレーベル<Brainfeeder>を立ち上げ、シーンで圧倒的な存在感を放つようになった。さらにその2年後となる2010年には、3枚目となる『Cosmogramma』をリリース。<Low End Theory>で鍛えられた重いベースミュージックを鳴らせ、自身の音楽に更なる上書きをした。
2012年、Flying Lotusは、4枚目となるアルバム『Until The Quiet Comes』を発表した。本作は、確かにいつもと同じ道具を用いてはいるが今までとはその方向性が異なる作品、という印象を受ける。鍵となっているのは、鮮やかな最先端のサウンドと独特な生のリズムの融合だ。
Flying Lotusの周囲には<Warp>や<Brainfeeder>など自身を刺激する存在が数多くある。M2「Getting There (feat. Niki Randa)」は、<Warp>より2011年に発売されたPrefuse73の女性ヴォーカルを大胆にフィーチャーしたアルバム『The Only She Chapters』を想起させ、M4「Heave(n)」は<Brainfeeder>からリリースしているTeebsとの親和性を感じさせる。また、M6「All The Secrets」からはJames Blake以降のポスト・ダブステップの流れも見て取れる。他のアーティストから受けた刺激を自身に取り込み作品として表すことは、刺激を受けたアーティストに対する最高のリスペクトとも言える。そして、こういったことが何度も重なってシーンは厚く大きくなっていく。LAのビートミュージック・シーンの層が厚いのは、<Low End Theory>をはじめとした最先端のイベントの数々、そして、その環境が閉鎖的ではなく新しいものにオープンで敏感であることが大きいのではないかと筆者は思う。
また、今作では、前作で確立した特有のベースライン、身体に脈々と流れるジャズのメロディ、自ら演奏した音や信頼する共演者が弾いた音、それらを重ねて鳴らしてみたり、引き算してみたりと、そうした音楽的な思考実験や、数多くの計算と偶然を感じ取ることができる。そこには、Flying Lotus特有のリズムの揺れが確実に存在している。その独特のリズムは、軽やかでありながら今作では主役と言っていいほどの存在感を放っている。
Flying Lotusは、普段音楽を聴くときは、生楽器で演奏された音楽しか聴かないという(1)。エレクトロやビートミュージックを聴くのは、クラブなどの現場だけ。そういった環境から生み出されたのが、このアルバムとなる。本作は、そうしたビートミュージック・シーンという外的要因と、自らのルーツでもあるジャズ、そして生音や生演奏といった内的要因とが絶妙に聯立している。そして、そこから生まれた独特のリズムの揺れは、何度ループしても飽きることはない。
註: (1)『サウンド&レコーディング・マガジン』(リットー・ミュージック)2012年10月号掲載の巻頭インタビューより(21頁)