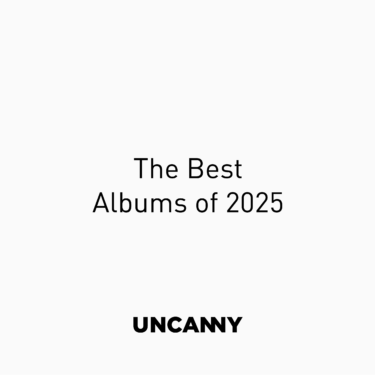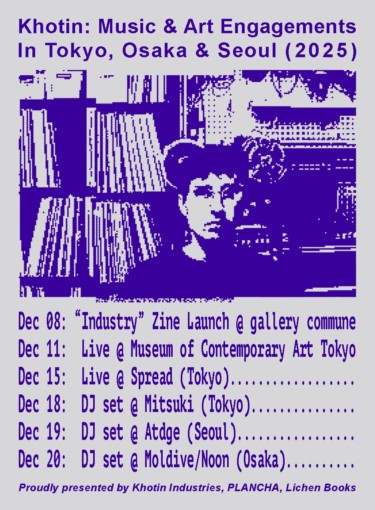- ARTIST:
-
Teen Daze
- TITLE:
- Glacier
- RELEASE DATE:
- 2013/9/17
- LABEL:
- PLANCHA / Lefse Records
- FIND IT AT:
- Amazon
- REVIEWSNovember/21/2013
-
【Review】Teen Daze | Glacier
逃避主義者のためのヒプナゴジックなベッドルーム・ミュージック―チルウェイヴがそのように定義づけられ、ひとつのジャンルとして浸透してから久しい。しかし、波の姿が常に変わりゆくように、インターネット・カルチャー由来の性格上、参加者たちによる際限なき差異化/細分化の果ての新たな局面―ポスト・チルウェイヴに突入して以降、Balam Acabのウィッチ・ハウス、How to Dress Wellや最近のToro Y Moiに象徴されるR&Bへの接近、もしくはチル&Bとも形容されるRhyeやInc.の動向、Neon Indianの享楽的なシンセ・ポップ、Blackbird Blackbirdのエレクトロニカ、インターネットの猥雑性を具現化したようなヴェイバーウェイヴ、ヒップホップに目を転ずればクラウド・ラップと新動向の枚挙には暇がなく、十把一絡げに扱うことも難しいのが現状だ。しかし、『Paracosm』にて、神話的創造力に彩られた逃避主義を開花させた元祖チルウェイヴ、Washed Outに象徴されるエスケイピズムに強く彩られた傾向も未だ衰えず、ヒプナゴジックなポスト・チルウェイヴはドリーム・ポップともその境界を曖昧にしながら領域を拡大し続け、現在も優れたアーティストを輩出し続けている。その中のひとりとされているのが、Teen Dazeである。
Teen Dazeは、カナダ出身のエレクトロニック系プロデューサー、Jamisonによるソロ・プロジェクトだ。「10代の日々」という名のノスタルジックな響きがチルウェイヴの追憶と共鳴するように、1stアルバム『All Of Us, Together』では潮騒の乱反射、ビーチの陽光を音に変換したような世界を展開し、趣を変え2ndアルバム『The Inner Mansions』は、16世紀の宗教書に着想を得たとおぼしき精神世界の拡張を、フォークトロニカとアンビエントの融合によって音で表現したような作品だった。そして、3枚目の今作『Glacier』の舞台は”Glacier”=「氷河」、北の極寒地帯である。『The Inner Mansions』収録のブライアン・イーノのカバー曲、「Always Returning」が示唆的だったように、今作ではTeen Daze流のアンビエント・アルバム、つまりエスケイピズムの究極形が追求されている。
本人自身、環境が作曲自体に影響を与えると供述しているように、北の自然の荘厳さを表現したかのようなコーラス・ワークによって幕を開ける「Alaska」、シンセサイザーによって反復されるたった4つの音色と、水の音が織りなす優雅なアンビエント「Walk」が想起させるのは『Ambient 1/Music For Airports』を始めとするイーノの諸作品であり、今作のアンビエント的性格がこれらの楽曲によって最も印象付けられている。さらに今作で想起されるのはイーノだけではない。全曲を通して極寒地帯が表現されるコンセプチュアルな性格、音像の雰囲気は、Biosphereが北の世界をモチーフにした古典的名盤『Substrata』の未来形であり、フィールド・レコーディングとシンセサイザーの乱反射が織りなす世界の構造は、Wolfgang VoigtことGASのアンビエントとも共通する面がある。音響面から言えば、Fennesz以降のドローンをも内包し得るアンビエントと、Taylor Deupreeの雪原を踏みしめる足音すらも響き渡るような繊細な音像の面影も感じられる。ひとつのアルバムの中でも多彩なアンビエント像が混じり合いつつ、ここでは一体になっていると言えるだろう。
さらに、Teen Daze流のアンビエントをはっきりと特徴づけているのは、イーノから連なるアンビエントの系譜のみならず、エレクトロニック・ミュージックのプロデューサーとしての感覚、ビート・ミュージック側からのアプローチである。「Autumnal」の背景に溶け込むように鳴り響く透き通ったビート、波の満ち引きを繰り返すような多彩なリズム・アプローチは、Mouse on Mars 、Boards of Canada~Tychoに至るエレクトロニカのビート感を引き継ぎつつ、独自に消化したものであり、Tychoの西海岸の陽射しに照らされたビートを極北の透き通った空気で濾過したような感覚がある。特に「Ice On The Windowsill」が提示する、ダブ・ステップ以降の感覚も加味したビート感に、流麗なピアノ・フレーズにアンビエントな色彩、ゴーストリーなボーカルが重なることで紡がれるビート像は、本作の白眉だ。ゆらめくチルウェイヴ的音響の向こう側から響く、漂白されたように清廉ながら硬質で変幻自在なビートは、ポスト・ダブステップ、ポスト・チルウェイヴ以降のプロデューサーで言えば、過去にリミックスワークも手掛けたXXYYXXやGiraffage、Slow Magicともある種の共通感覚を見出せそうなものがある。「Leaf Canopy」では4つ打ちハウスも取り入れていて、ビートの面でも多彩な顔を覗かせている。
しかし、こうして眺めてみると、一応最初にTeen Dazeをヒプナゴジックなポスト・チルウェイヴの枠組みに置いたが、「ポスト・チルウェイヴ」という言葉の曖昧さがより意識される結果ともなった。そもそも一緒くたに形容することは不可能な音楽の総体を扱うための便宜的なジャンル名に過ぎないにしろ、「ポスト」の意味するものは「~以降」ということであり、そこにこの言葉が形容している音楽の批評性がある。「ポスト・チルウェイヴ」とはひとつのジャンルではなく、チルウェイヴという引力圏からの逃走、弁証法的な運動と言ってしまってもいいかもしれない。その運動は常に揺らめきながら、チルウェイヴを拡張すると共に、半分その身を他の領域へとわざと逸脱させているのだ。そこでは常に文脈の揺らぎと音楽の揺らぎが連動しつつ状況は変化し続ける運命にあり、そこにこの運動の面白さも潜んでいると言える。
視点を引いてTeen Dazeの活動全体を振り返ってみると、1stアルバム以前の作品『My Bedroom Floor』ではクリスマス風エレクトロ、2011年のEP『A Silent Planet』ではクラウトロックの影響、ネット・リリース限定のEP『The House On The Mountain』ではポストロック的アプローチが垣間見える等、1つの名義の内にあってもそこには多彩な顔があった。彼の音楽の逃避主義的な側面はチルウェイヴ的な受容も可能にするが、それだけに留まらない部分が彼の音楽を最も面白くしていることも、また間違いない事実であろう。そして、その事実こそがまたまさしく「ポスト・チルウェイヴ」であることの、逆説的な証明にもなるのではないだろうか?
文:宮下瑠
1992年生まれ。UNCANNY編集部員。得意分野は、洋楽・邦楽問わずアンダーグラウンドから最新インディーズまで。青山学院大学総合文化政策学部在籍。