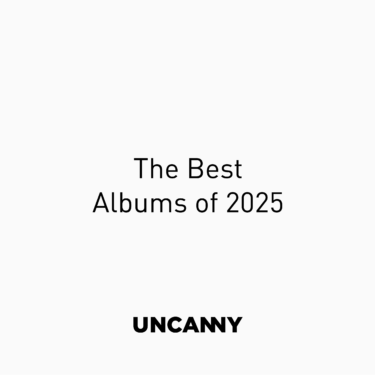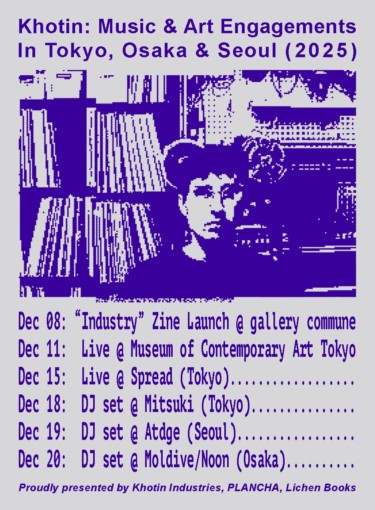- INTERVIEWSDecember/20/2021
-
[Interview]Kumi Takahara - “See – through”

東京に生まれ、3歳からヴァイオリンを始め、国立音楽大学音楽学部弦楽器専修を首席で卒業。その後、ウィーンに渡り、ヨーロッパを中心に音楽活動を行う。帰国後はクラシックでの演奏活動と並行し、楽曲提供やプロデュース、映像作品のディレクションまで、ヴァイオリニストとして演奏のみにとどまらず、多岐に渡る活動を展開──。
今年2月に〈FLAU〉からアルバム『See-through』をリリースした、Kumi Takahara。音楽家として華麗な経歴を誇る彼女にとって、本作はそのデビュー作となるという。制作開始からリリースまで5年の歳月をかけたというアルバムには、ポスト・クラシカルの要素を軸にしながらも、多彩な世界が広がる楽曲がそろっている。今回のインタビューでは、こうした作品たちに佇む不思議な魅力の背景を紐解き、自身のルーツに加え、アルバムの楽曲や制作過程について詳しく語ってもらった。
__大学卒業後は、ウィーンを拠点に、ヨーロッパを中心にコンサートやライブなど音楽活動を行なっていたとのことですが、そうした海外での活動はどのような経験でしたか。
渡欧する前と後では音楽への向かい方というか、大袈裟に言えば、生き方も変わるような重要な経験がいくつもありました。当時の日記を読み返すと、「音楽はいとも簡単に国境を越える」と思うような体験を繰り返していました。
ウィーンは移民も多く、さまざまな国の人と出会いましたが、英語の通じない人も多かったんです。例えば、公園にいるアコーディオン弾きたちの共通言語はフランス語でしたが、それでも楽器があればセッションして仲良くなれたし、人間性に触れることもできました。ポーランドの田舎町に行った時には、酒場のジュークボックスでパティ・スミスをかけたら他の客が踊り始めたり。だからもっと言えば、「音楽は言語も関係なく国境を越える」のだと思います。
もう一つ、貴重な経験となっているのは、ヴァイオリン本来の鳴り方というものを知れたことです。室内楽のプロジェクトに参加してポーランドの教会で演奏することが何度かあったのですが、教会の建物はどこも天井が高く、独特の深い残響が素晴らしくて。そもそも西洋の弦楽器はこういう場所で演奏する前提で発展してきたんですよね。どの教会もあまりに自然に音楽ホールになるので、「祈ること」と「音楽」との密接さも肌で感じました。
どちらも当たり前の事のようですが、日本で習い事としてヴァイオリンを始めて、音楽学校で学んで…という過程の中では気づけなかったことです。自分にとって大切な、かけがえの無い経験になりました。
__〈FLAU〉の公式サイトでは、この時期について「この頃から弦楽器の可能性をクラシック以外にも求め、自身の作曲活動もスタートさせる」とあります。また、帰国後は、ヴァイオリニストとしてだけではなく、さまざまな音楽活動を開始していますが、こうした方向に向かう、何かきっかけなどはありましたか。
それまではヴァイオリニストとしてどれだけ良い音を出せるか突き詰める、というようなことを続けていたので、作曲は私にとってはまったく違うチャンネルで、それをする自分なんて想像もしていませんでした。でもある時、水があふれるような感覚で自分でも驚くほど突然、わーっと曲を作り始めたんです。予兆といえば、10日間不眠症のような状態だったことくらいなのですが、本当に突然のことでした。
きっかけはそこから10年前まで遡りますが、当時19歳だった姉が急逝してしまったことで、ウィーンに行ってからずっと自分の深淵を見つめるような時間を持っていて、音楽を聴く時も心の中身が剥き出しのような状態で……。たぶん蓄積されたものが精神のキャパシティを越えたのだと思います。姉への気持ちが10年かけてその頃ピークを迎えていて、行きどころのない気持ちを曲作りで消化したんですね。姉がロックバンドのボーカリストで曲も作っていた人だったので、その影響も大きいと思います。

__今年2月に発表されたデビューアルバム『See-through』について聞かせてください。プレスリリースでは、下記のような解説がありました。
“2016年、高原の暮らすアパートで最も静かな場所であるバスルームで録音がスタートしました。バスタオルを吸音材として使用し、シンクの上にマイクを設置して、洗濯機の上にノートパソコンを置いてバランスをとりながら録音されたというデモを元に[…] ”
このように始まった今回のアルバムを制作する上で、楽曲一つひとつに共通しているテーマや全体像としてのテーマはありますか。
制作中このアルバムの仮タイトルはずっと「Daydreams」でした。夢か空想か、はたまた子供の頃の記憶か何か、誰しも無意識に持っている、心の奥底にあるような情景があると思うのですが、そういう景色が見えてくるような音楽を作ろう、というのが10曲に通じるテーマになっています。
宅録で作る、というのは最初から決めていて、何年も一人の空間で録り進めてきました。内に向かっていく制作でしたが、個人的な音楽でありつつも、私小説的になりすぎないよう注意していましたね。その塩梅が難しくて、作曲を始めた頃は「自分の音楽を触られたくない」とかなり閉鎖的でしたが、聴き手にふわっと委ねるところまで、ようやく持ってこれました。それは、この音楽は私のものでありながら、同時に聴く人のものでもある、という感覚です。内側に向かいつつも、外向きなもの。誰かの心の内側にフィットして、そっと触れられるような音だったら良いなと常に思っています。
__TakaharaさんのInstagramでは、現在、1曲ずつ収録曲の解説がポストされています(2021年11月1日の時点では、7曲目の「Chant」まで)。すべて興味深い解説なのですが、例えば、「Roll」の解説には「車窓から眺める景色と音楽との親和性」と「輪廻」といったことが記されていますが、より詳しく教えてください。
徒歩や列車やバスや飛行機、手段はさまざまですが、移動中にぼーっと景色を眺めながらイヤフォンで音楽を聴くことがとても好きなんです。その状態であれば何時間でも、例えば長時間のフライトだったとしても飽きることなく熱中できるので、移動をすることと音楽を聴くことはなんて良い組み合わせなんだろうと、昔から感じていました。
「居た場所」と「向かう場所」の間にいる宙ぶらりんの不安定さが、心の在り処を探るのにちょうどよいのかなと思います。長距離移動の無い日常であっても、音楽を聴くためだけに電車に乗ったり、何時間も歩き続けたりしていました。新しいデモができたら、とりあえず移動をしながら聴いて、部屋とは違う聴こえ方を味わうことにしています。
そんな移動中の情景を曲にしたのがこの「Roll」です。右、左と交互に進み続ける足や、電車の窓から見下ろす街並みだったり。ぐるぐると際限なく続くピアノのメロディラインには円を描くイメージもあって、そこから終わりのない輪廻を連想できる。ループものの音楽は聴くのも大好きなのですが、その歴史は300年前のパッヘルベル作曲のカノンまで遡れますよね。そうした繰り返す心地よさって、昔からあったのだと思います。
__「Kai-kou」 は、同じくInstagramの解説では、「邂逅」という意味とのことですが、収録曲のなかでも極めてドラマチックな楽曲に仕上げられているように思います。「人生が動くような邂逅」とも記述されていますが、この曲で描かれる世界観について詳しく聞かせてください。
他の曲はどれも、海や森、街中など具体的なイメージがある情景音楽なのですが、この曲はちょっと違っていて事象を描くような感覚だったのでそう感じられたのかもしれないです。人と出会うことは誰にでも何度も訪れる瞬間ですが、その中でもしそれがずっと続く特別な縁ならば、それは一生で何度も振り返ることになる、とても重要な瞬間になります。この曲ではそんな長い人生のドラマを凝縮しています。チャイコフスキーが作った「ある偉大な芸術家のために」という曲がありますが、つまりこれは、そういったタイプの曲なんです。
__「Sea」は、まだ現時点で解説がInstagramにポストされていませんが、タイトルと波の音から、海がテーマになっているように理解できます。そのまま「Tide」へとシームレスに続きますが、先行シングルとなった「Tide」のテーマについて教えてください。また、ausが参加していますが、ausの参加によって楽器にどのような効果や影響が加えられたと思いますか。
つい最近ポストしたところなのですが、「Sea」は私自身がずっと心の中で大切にしている、ある景色とリンクしている曲なんです。人気のない静かな海辺で、空は曇っていて、少しぼんやりしていて、遠くの木のあたりを鳥が飛んでいるのが見えるような場所です。そこには懐かしいような不思議な心地よさがあるので、たびたび思い浮かべてはその感覚に浸っていました。夢で見たのか、過去に映画などで観たのか、ただの想像の世界なのかもわかりません。
「Sea」の終わりにはバイオリンのフラジオ奏法の高音を入れているのですが、浜辺の遠くの方に何か光るものが見える様子を表したものです。その光の方に歩いていくと、隣の海岸に着くような感覚で「Tide」の世界に移ってゆきます。
「Sea」では波打ち際を歩いていましたが、「Tide」ではじゃぶじゃぶと海の中に入っていって渦巻く轟音に飲み込まれます。トラック数が多くて大変でしたが、オーケストラ並みの大きなエネルギーが多重録音で作り出せたように思っています。フーガの技法で弦楽器を重ねていくやり方は新たな挑みでしたが、耳元でささやくような、その場で漂うような、抑揚の少ない曲が多い中で、エモーショナルなところまで表現したという点でも新境地でした。
このアルバムの中で一番手のかかった曲で、4年ほどかけて何度も作り直して5パターンくらいデモ音源があるんです。ausさんにその都度アイデアを出してもらっていました。最初はもっと音数も少なくてクラシカルな構成だったんです。そこから潮にのまれながら、まさに助け舟を出してもらって、一人では辿り着くことのできなかった未知の島へ泳ぎ着いた……というような感じですね。溺れかけながらも……。
その最終段階のデモをausさんに預けて、盛り上がる部分からアウトロにかけてを中心にエディットしてもらいました。具体的に言えば、シンセなどの空間を埋める音をいくつも重ねてもらっています。
__「Tide」は、ミュージックビデオも公開されていますが、“潮”という意味を持つ曲名の通り、潮の流れの描写が基調とされています。映像の中には、結晶や雲の描写もありますが、それはどのようなものを表象したのでしょうか。
潮というのは単なる景色ではなく、心の渦ということでもあるので、気持ちがぐーっと持っていかれるような景色なら何でもマッチするんです。韓国の映像作家のRayaさんがいろいろなシーンを集めてくれて、それが早送りや巻き戻しとともにコラージュされることでイメージや時間に固定されない良い意味で抽象的な、素敵な映像になりました。そして、音楽でも映像でも、個々で解釈してもらえる余白を残すことは、大切なことだと思います。
__続く8月に発表された、本作のリミックスアルバム『See-through Remixes』では、先行シングルにも収録されていたEarth Traxをはじめ、〈12th Isle〉や〈Not Not Fun〉から作品をリリースしているフランスのVague Imaginairesや、〈Dauw〉からリリースしているUKのDylan Hennerなど、さまざまな国を拠点とするアーティストが多数参加しています。これらのリミックスワークで、特に印象深かった作品はどのリミックスですか。また、その理由を聞かせてください。
みなさんどれも純度の高い音楽で、それぞれめちゃくちゃ好みなので選びづらいのですが、聴いた時の衝撃が強かった一曲をあげるとすると、Hviledagさんの「Chant」でしょうか。この曲のオリジナルはTape Loop Orchestraさんに編曲してもらっていますが、リミックスでは元々の録音の質感からあまり加工されず、生々しいままの楽器と声が使ってあるんですね。音数も少なく余白のある作りですが、凄まじい引力の空間が出来上がっています。原曲の中のごく限られた部分だけが切り取られて構成されていますが、それでもドラマチックな作りになっているんです。
元々私自身の作曲の手癖としてコードやメロディで展開をつけすぎてしまうところがあったのですが、ここまで削いでも良いものになのかという驚きがありました。バイオリンのピチカートの音が面白いコード感で重ねられていて、どこかの民族楽器のような不思議な響きがするところも好きです。知り尽くした楽器だと思っていましたが、まだまだ新しい響きの可能性を見つけていきたいと思いました。
リミックス集は本当にどの曲も素晴らしくて、自分にとって宝物のような作品になりました。
__今回のリリースに合わせて発表された、repeat patternによるアーティスト写真の中には、山々が見える自然を背景に大きなビニールのようなものに包まれた写真があり、「Tide」のアートワークにもなっていますが、一つの作品としても捉えられるように思います。撮影のエピソードも含め、この写真について詳しく聞かせてください。
あの写真は群馬の山で撮ってもらいました。ビニールを使うのは素敵なアイデアですよね。アルバムの透かし見るイメージが具現化されているようでとても気に入っています。大きなビニールを張ったポールを立ててもらって撮影しています。実際のところ風任せなので、私は立って、目の前ではためいたり、顔に纏わりつくビニールを薄目で眺めたりしていただけなのですが、repeat patternさんが根気強くシャッターを押してくれて、いつの間にか最高の画を収めてくれていました。
ビニールという人工的な素材を使っていますが、この写真には有機的なエネルギーが溢れていると思います。私は現代的な音作りの時にも生楽器にこだわってなるべくフィジカルに録音をしているので、そのあたりもうまく表現してもらえたと思います。

__最後に、今後の活動について教えてください。
今回のアルバムが私のデビュー作となりますが、制作開始からリリースまで5年もかかってしまっていて……。慎重に作り直しを重ねてきたのですが、作曲家としてやっとスタートを切ることができたので、これからはもう少し制作のスピードを上げたいと思っています。具体的には、「Tide」のように弦楽器が主体となるもの、そして「Log」のようなビートがあるものを開拓していきたいです。現代音楽やアンビエントの流れを汲みつつ、好みのサウンドを追求していこうと思います。
制作活動と並行してライブ活動もやっていきたいのですが、こうした時期なので、新しい試みもはじめています。まず、今回の『See-through』のリミックス集のリリースに向けて、夏頃から定期的にインスタライブで演奏の配信をしてみたんです。部屋で一人でループステーションを使ってピアノや声、ヴァイオリン、チェロなど色んな音を重ねていくというものなのですが、それが意外にもなかなか楽しくて。それをよりハイクオリティなライブ動画として収録しようとはじめたのが最近YouTubeにアップし始めたシリーズです。
宅録での制作は、部屋でひとりで遊んでいるようなものなのですが、このライブ動画シリーズは完全にその延長線上です。部屋からの発信が世界に向かっていく、というのが面白いですね。いろんな場所に入口を作って、自分の音楽がたくさんの人の耳に触れられるといいなと思います。
今回の一連のリリースによって自分の音楽の幅も広がりました。新たな可能性も見えてきたので、この先どんなものが生まれるか自分でも楽しみです。

See-through:
1. Artegio
2. Ditty
3. Nostalgia
4. Roll
5. Chime
6. Kai-kou
7. Chant
8. Sea
9. Tide
10. Log

See-through Remixes:
1. Artegio (Machinone Remix)
2. Ditty (Dylan Henner Remix)
3. Nostalgia (Vague Imaginaires Remix)
4. Roll (Zoe Polanski Remix)
5. Chime (Federico Durand Remix)
6. Kai-kou (Porya Hatami Remix)
7. Chant (Hviledag Rework)
8. Sea (Roméo Poirier Rework)
9. Tide (Bartosz Kruczyński Remix)
10. Log (The Humble Bee Remix)
11. Tide (Earth Trax Remix)
Photo by repeat pattern
編集:東海林修(UNCANNY)
![[Interview]Kumi Takahara - “See – through”|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)