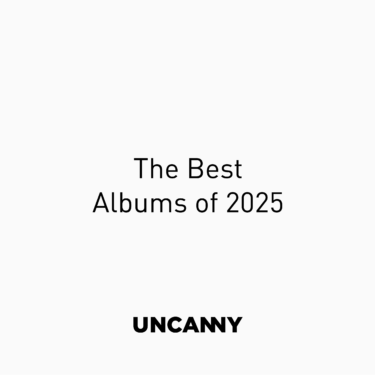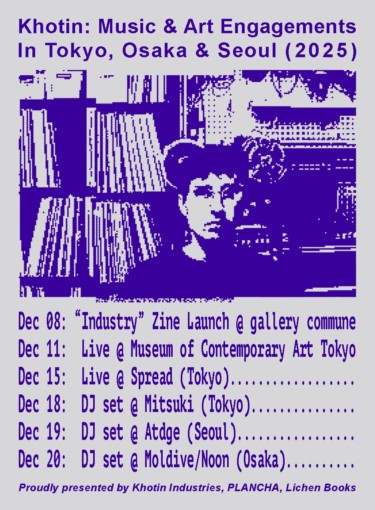- INTERVIEWSOctober/18/2019
-
[Interview]Floating Points – “Crush”

「豊かな社会」と表された、かつての時代──。疲労すら「消費される疲労」と位置づけられた当時の諸問題は、すでに一部の者が語るだけのものではなく、今や誰もが認識する自明のものとなっている。ソーシャルネットワークに見られるような個から、国家単位を個とする闘争まで、欲望を隠すこともなく他者を冷たく断絶するさま。それらは望まずとも、すでにここは平坦な戦いの場ではないというリアリティそのものを繰り返し何度でも突きつけてくる。
ロンドンを拠点とする音楽家、Floating Points(フローティング・ポインツ)は、最新作『Crush』において、こうした私たちの世界の過酷なリアリティに対峙するかのような緊迫したサウンドを表現している。これらの楽曲はダンスフロアという場所で機能し、肉体というフィジカルに呼応しながら、私たちを鬱状態から救済するかのようでもある。2015年の前作『Eleania』から4年ぶり、今年新たに契約した〈Ninja Tune〉からのリリースとなった本作は、まさに本人が語るように「音楽の即時性や、ダンスフロアにいるときにリスナーが音楽の中に入り込んでしまうような感覚」を捉えたものだという。そうした本作の鍵となる自身の「初期衝動への原点回帰」につながる様々な心象が楽曲となって描き出されている。(*1)
__神経科学のPh.D.(博士号)を持っているそうですね。例えば、音楽のほかに、科学者としての仕事もしているのでしょうか。
博士課程に在籍していたときに同時に音楽もやっていて、Ph.D.を取得した頃には、音楽で生活していこうと決めて、音楽の道に進んだんだ。正直、科学の世界では僕を必要としていないと思うから(笑)。実は、研究は続けているんだけど。自分の興味のあるところが、神経科学のなかでも本当に小さな一部の分野で……。僕が研究してきたこととか、自分のプロジェクトに興味を持ってくれるような研究所が、世界で4つだけなんだ。そのうち2つが日本にあるんだけどね(笑)。本当に狭いところをこれまで研究してきたので。
__なるほど。
当時は、家と研究所とスタジオと毎日行ったり来たりで。毎朝7時に家から研究所に行って、夜の7時にスタジオに行って、帰って少し寝てまた研究所に戻ってっていう毎日の繰り返しで。それ以外は何もできないような毎日だったね。でも、すごく忍耐強いガールフレンドがいて、彼女が僕を支えてくれたんだ。本当に優しい彼女で。今も支えてもらっているよ。科学も、音楽も、彼女のことも、みんな本当に大好きだからね。そうやって何かを愛しているときは、必ずすべてうまくいくようにと、全力を尽くすことができるんだ。
__10月にリリースされるアルバムについて聞かせてください。この『Crush』というタイトルはどういう意味づけなのでしょうか。
“Crush”っていう言葉は、「壊す」っていう意味を最初に思い浮かぶと思うんだけど、英語だと「片思い」や「ちょっとあの人、気になるな」っていう気持ちを“Crush”って言うような、そういった意味合いもあるんだ。どこか愛情がある、気持ちが暖かくなるような言葉としてね。でも、やはり裏を返せば「壊す」という意味がそこにはあって。だからこの言葉は、ここでは、“ゆっくりとした暴力”というイメージなんだ。例えば、ネジをゆっくり回して、どんどんテンションが強くなっていって最終的に壊れるというようなね。
このアルバムを作っていたときに、ドナルド・トランプのことや、そういう政治的な問題のニュースがたくさん報道されていたんだけど、彼らがネジをゆっくりゆっくり回して、僕たちを最終的に壊してしまうんじゃないかっていう気持ちになって。それでこのタイトルをつけたんだ。このままこれが続いたら世界はどうなるんだろう、いつか全部壊れてしまうのかなって。実際こうしている間にも、環境問題の観点でも、文字通り世界が破壊されているよね。 “Crush”という言葉には、そうした意味が込められているんだ。
__そういったタイトルの意味は、アルバム全体のテーマにもつながっているのでしょうか。
このアルバムは5週間ぐらいで作り上げたんだけど、その5週間ずっとニュースを見たり読んだりしていて、ちょうどUKがブレグジットの問題に直面していて、悲しいような、情けないような、おかしな状況になっていたんだ。だから元々は、意図的に“Crush”というテーマに沿って作っていたわけじゃないんだけど、自然にそのテーマに沿った作品になっているんじゃないかなと思う。
__イギリスがEUを離脱するかどうかといった、国内の対立ですね。
とても悲しかったよ。UKにとってはとても大きな問題だと思う。けっきょく投票した人たちが最終的に痛い目を見る羽目になってしまうと思うし、投票した人はバカだってみんな言うけど、彼らはバカなんじゃなくて、僕は本当に嘘をつかれて騙されたんだと思っているんだ。
UKは、自分で自分を傷つける結果になってしまっていると僕は思う。僕はアーティストだからUKから出ようと思えば世界の何処へでもいつでも行けるけど、でもやっぱりUKのなかでそんなことができる人なんてほとんどいない。どんどんUKが世界から離れていって、ますますUKのなかの世界が小さくなっていって、逃げ場がない人のことを考えると本当に心が痛むね。
ここ2、3年でUKに限らず多くの国が孤立するようになっているというか、自分たちのなかだけで自分たちの文化や経済を守ろうとしているのがすごく目立っているように思う。この時代でそれが起きるのは悲しいことだと思うし、これから生まれてくる若い世代が今の大人のせいですごく閉じこもった世界のなかで生きていかないといけなくなると思うと、悲しい気持ちになるんだ。
“Crush”は、天井が降りてきて壁も迫ってきて、自分の世界が狭くなっていく、そうした世界のなかで潰されていくというイメージもあるね。じゃあ、それでどこに行けばいいのって。もう革命なんて起こせないくらい潰されてしまっているようにも思うんだ。
僕は活動家でもないし革命家でもないけど、むしろ自分の世代の人がみんなそうだからいけないのかなとも思う。みんな諦めて静かに見ているだけだから、そんななかでも革命的なことを起こそうとする人の姿を見ると勇気をもらえるよ。
__それでは次に、リードシングルの「LesAlpx」ですが、この曲はどのような経緯で制作された作品なのでしょうか。
彼女の家がアルプスにあって、すごい小さなかわいらしい木造の家なんだけど、最初はそこで作り始めた曲なんだ。その家はアルプスの、イタリアとフランスの国境の方にあってね。そこで自然と作り始めて、ある程度できたらロンドンの自分のスタジオに持ち帰って完成させたんだ。“LesAlpx”は、フランス語でアルプスって意味なんだけど、スペルは正しくないなぁ(笑)。
__アルバムの後半では、「ENVIRONMENTS」「BIRTH」「SEA-WATCH」という、3つのタイトルが続きますが、これらは連続した作品なのでしょうか。
そういう意図はないんだ。その3曲も2週間くらいで作りあげたんだ。例えば「SEA-WATCH」は、海に船を出して難民を助けに行く人道支援の団体があって、それをイメージした作品。Carola Racketeという女性の船長がいて、彼女は溺れて死ぬはずだった数百人もの難民を自分の船に乗せて、反対側のイタリアまで連れていくんだ。彼女の行為は違法かもしれないけど、人を救うという重要なことをしている。僕から見たら、彼女はヒーローだよ。「かわいそうだな」とか「しょうがない」と、ただ言っているだけの人と違って、実際に行動に起こして助けることで、彼女は法的には犯罪者になってしまうけど、僕はまったくそうは思わないね。
難民の人たちが「助けて」と言って来ているのに、国がそれを受け入れないというのは、僕はすごく悲しいことだと思う。その人たちが苦しんでいるのって、自分たちがその人たちの国に爆弾を落とすような行動をとっているからであって、自分たちが起こしている罪を償おうとしない国に対して、すごく悲しい気持ちになる。この曲は、そうした深い意味があるんだ。
__「BIRTH」についても聞かせてください。
その曲を作っているタイミングで、ちょうど僕の周りの人たちが子供を産んでいて、たくさんの赤ちゃんが誕生していたので、その人たち全員のために作った曲なんだ。子供が生まれたと聞くと、いろんな苦しいことや世界問題から救われた気持ちになるんだよね。環境問題、要するに地球が終わっていっているような状況になっているなかで、新しい命、その問題に戦ってくれる次の世代が生まれてくることは、すごく大事なことだと思う。
__アートワークは、バルセロナのハミル・インダストリーズが手掛けていますね。内容については、どのような依頼をしたのでしょうか。
もともとすごく仲の良い友だちなんだ。よくあるようなくだらない会話をしょっちゅうしていてね。8年くらい前にYouTubeを見ていて、ある子供がレーザーペンを使って暗いところで光る紙に自分の名前を書く動画があったんだ。それを見て、自分もやってみたいと思って、前回のアルバムでは、それを依頼しだんだ。
今回のアルバムは、大きなシャボン玉を作る人を見ているときに思いついたんだ。シャボン玉の表面って色が綺麗だよね。ガソリンが水に浮いているみたいな。それでさっそく電話をしてね。まず、シャボン玉のフィルムを作って、マクロレンズでその動画を撮るんだけど、その間にずっと自分のシンセサイザーから鳴っているドラムの振動で、そのシャボン玉にちょっとずつ空気を入れていって模様を作るという作業をやっているんだ。その動画を写真にしたのが、今回のアートワークになっているんだ。一緒にやるのがすごく楽しいんだよ。
__音楽制作だけではなく、DJとしても精力的な活動をしていますね。あなたにとって、DJとしてのパフォーマンスをすることの魅力について教えてください。
自分にとっては、DJをやるっていうのはすごく自分勝手なことだと感じている。なんでそう思うかというと、やっぱり僕はみんなと同じで音楽がただ本当に大好きなだけで、元々はレコードをいっぱい持っていたから、パーティーでそのレコードを回したりとかしていただけだし。今も本当にもう、自分がそのときに聴きたいものを自分の聴きたい音量で流しているだけなんだけど、ソウルからディスコにいってブラジリアンからテクノにいって、いろんなジャンルを流すのも、けっきょくすごく僕が自分勝手だからなんだよ。
普通に音楽が好きな人もそうだと思うけど、いろんな音楽を聴くから、本当に純粋に自分勝手な部分が魅力なんだって思うね。それと、日本に来てレコードショップに行って、日本のレコードを全部奪うように買って帰るのが大好きさ(笑)。
__いわゆるクラブという場所で場を作るということに関してはどのように考えていますか。
まずその空間を作りあげるのが、本当に楽しい。僕はそのDJセットを出来るだけ長くやりたいし、一晩中クラブを全部自分の音楽だけでもう全部やりきりたいと思ってDJをしているよ。クラブっていうのは空っぽの部屋で、それをちょっとずつゼロから作り上げていく。アンビエントから始めて少しずつ壁をデコレーションしていくように、慎重に、もちろん自分勝手にその部屋を作り上げる。要するにそうやって空間を作りあげるっていうのが、一番楽しいと感じてるね。
例えば、できるだけ長く落ち着いた空間をつくって、8時間セットだったら2時間ずっとアンビエントにしてみる。そうすると、みんなから「もっと来いよ」っていうエネルギーを感じてくるから、じらしながら、少しずつビルドアップしていくんだ。それからしばらくすると、もう手に持っているんだ。このレコードをかければフロアが爆発するっていうものをね。それをかける瞬間が一番楽しい。それをかけた瞬間にパーティーが始まって、みんな踊りまくるような…でも、だから誰かのあとにDJをするのはすごく難しい。前のDJがすでに空間を作ってしまっているからね。それを自分のものにするのは難しいなといつも思うよ。
__最後の質問になります。科学者であり音楽家であるあなたにとって、科学で乗り越えることのできる部分と音楽で乗り越えることのできる部分があるとしたら、それをどのように考えているのでしょうか。
音楽、アート、そしてカルチャーというものは生きていく意味を与えてくれるもの、そして、科学は僕たちが生き延びるために必要なものだと思う。科学があれば生き延びることができるし、アートや音楽があれば生きていこうと思える。でも、科学だけじゃ生きている意味はない。生かされているだけになってしまうからね。どちらも必要なもので、どちらかが欠けると何も存在しなくなってしまうと思うよ。それと、科学のなかにある美しさを見出すことができたとき、僕は喜びを感じるんだ。
__科学のなかにある美しさとは何でしょうか。
例えば、自然界のなかのシンメトリー。どちらも同じ数で、真ん中で割っても同じに見える花びらや、それらの美しさ。現代を生きているなかで人間が美しいと思うものの原点は、だいたい自然にあったものからできている。音楽も科学も自然界のなかの美しいものを持ってきて、音楽やアートだったらそれで自分の作品を作ったりする。科学の場合は、それを研究して生きていくために使っている。つまり、何でも自然から持ってきているものだから、そこも似ているなと思うね。
(2019.8.17、東京にて)
*1 Floating Points自身による本作『Crush』の解説は、Beatinkのプレスリリースより引用。

Crush:
01. Falaise
02. Last Bloom
03. Anasickmodular
04. Requiem for CS70 and Strings
05. Karakul
06. LesAlpx
07. Bias
08. Environments
09. Birth
10. Sea-Watch
11. Apoptose Pt1
12. Apoptose Pt2
[Bonus Track for Japan (BRC-615LTD/BRC-615)]
13. LesAlpx Dub – (JAPANESE SPECIAL EDITION)
通訳:エイミー藤木
編集アシスタント:杉田聖司, 大嶺舞, 金子マナ, 佐藤圭悟, 松永千佳(UNCANNY, 青山学院大学総合文化政策学部)
Photo by Dan Medhurst
![[Interview]Floating Points – “Crush”|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)