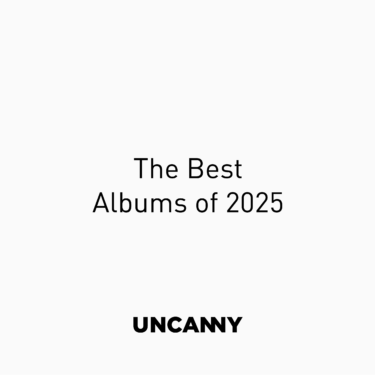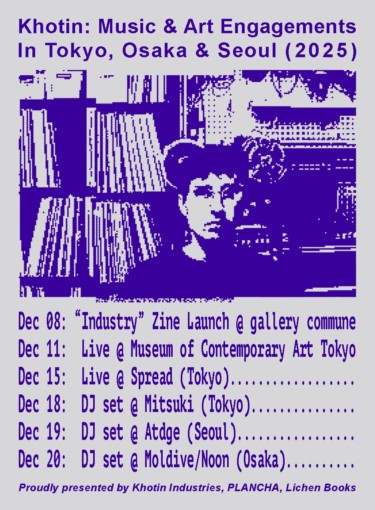- EVENT REPORTSMay/09/2019
-
[Live Report]Sevdaliza “Sevdaliza’s The Great Hope Design” ──音楽と身体が絡み合う舞台表現

時折、我々の肉体は、精神に沿ってデザインをされたものではないのだと気づくときがある。誰しも、少なくとも一つくらいは、自分の肉体と精神の不和についての悩みを持っているだろうし、それぞれの一体化を図ろうとすれば、どういった形にせよ不断の努力が必要とされ、そこには底知れない苦しみと自己否定の連鎖が横たわっている。後天的に統合を目指すことは不可能ではないが、逆に言えば、我々は望まない身体、あるいは精神にいつだって戻れてしまう。意思と行為が反発し続けることに抗えないまま、それでも他者に差し出せるのは行為の結果でしかない。そんな煉獄の回廊をぐるぐると歩きながら、ここを抜け出せるのであれば、アイデンティティすら放棄しても構わないと思うときがある。
望むにしろ望まないにしろ、自分の肉体は自分のものであり、貸与されたものではない。どちらか片方だけを捨てることは、けっきょく(いまのところは)できないし、我々の多くは、両方を捨てられないからこそ生きている。その「今のところは生きている」という結果だけを引き受けて、明日もきっと生きているだろうと仮定している。

2019年4月8日、「Red Bull Music Festival 2019」のプログラムの一つとして、南青山のSpiral Hallにて、アーティストのSevdalizaによるライブパフォーマンスイベント「Sevdaliza’s The Great Hope Design」が開催された。舞台演出を彼女自身が手がけたという本ステージは、念入りに組み上げられた構築美と、眼前でリアルタイムに肉体が絡み合う緊張感に満たされた、特別な体験だった。
ステージ上で演奏されたチェロとキーボードによる厳かなライブ・イントロの後、袖から登場したSevdalizaは、女体をモチーフにした立体デザインのドレスを「着用」していた。胸と下半身を強調した、「機能」としての女性性を想起させるその衣装を纏いながら、彼女はそれも自分の肉体であるかのように振る舞い、果敢に声をあげた。

ライブの要所に登場し、Sevdalizaの世界を拡張するコンテンポラリーダンサーもまた、演出を際立たせる存在として機能していた。彼女らは、イニシアチブを取り合うのではなく、歌う主体と踊る主体として相互に存在していた。Sevdalizaが声を上げるために出来なかった行為を、まるでダンサーが乗っ取り、拡張しているようにもみえた。


ライブが中盤に差し掛かると、女体をモチーフにした奇妙な衣装から、相反して肉体を過剰に隠すような、ワインレッドとグレーのドレスに着替えて再登場する。彼女のパフォーマンスはより幅を広げ、キーボードの弾き語りや、より挑戦的で過激なダンスにも発展する。時折、ステージの背景に、プロジェクション・マッピングの要領で彼女の顔が大きく映される。そこに映る彼女の表情は細部までコントロールされきっており、シンガーである以上にアーティストとして舞台に立ち向かう彼女の姿勢がそこから伺えた。それと同時に、Sevdalizaの眼前に立ち、その表情を微細なところまで追いかけ、プロジェクターに映そうとするカメラマンや、奏者が同時に立っているステージを緩急自在に飛び回るダンサーの存在が、現場の緊張感を煽り、より我々を眼前の出来事に没入させた。
音楽と肉体表現が絡み合う演劇的な表現と、演者であるSevdaliza、その舞台演出をサポートする人員が舞台上に同居するこのライブアクトは、外側と内側が交わり、それらが物理的に統制されるのではなく、それぞれの表現を複雑に絡み合わせることで、一つの大枠の表現に立ち向かうように感じられた。音楽の表現力を肉体によって拡張し──これこそがライブパフォーマンスの醍醐味である──、そして肉体の表現は舞台装置(そして、舞台を立ち支える人々)の存在によって拡張される。人が何重にも入り混じる故に、時には舞台から緊張感が漂う瞬間もあったが、ステージにはそういった内外の複雑な文脈すら飲み込ませるような迫力と説得力が生まれていた。そして、舞台でも特に印象的に歌い上げられた楽曲「Human」の通り、統制されきらないモジュールが肉体の隅々まで組み込まれている存在こそが私たち人間であり、そこに存在する人間すべてが「人間以上の存在ではない」ようであった。

1992年生まれ。UNCANNY編集部。ネットレーベル中心のカルチャーの中で育ち、自身でも楽曲制作/DJ活動を行なっている。青山学院大学総合文化政策学部卒業。
![[Live Report]Sevdaliza “Sevdaliza’s The Great Hope Design” ──音楽と身体が絡み合う舞台表現|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)