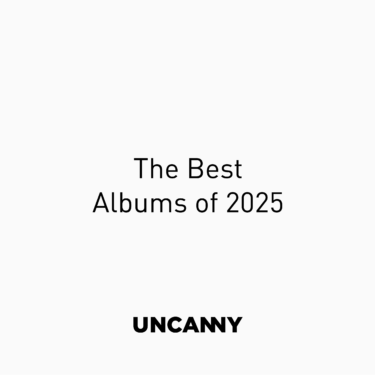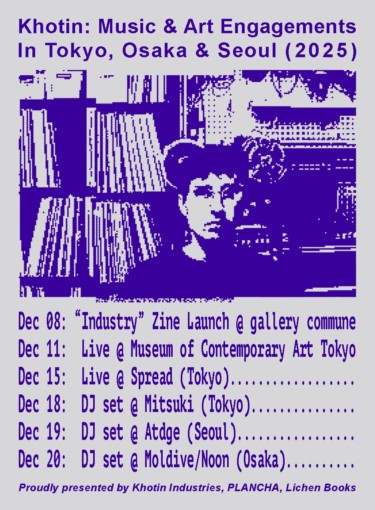- EVENT REPORTSOctober/22/2018
-
[Event Report]A CONVERSATION WITH DAITO MANABE──真鍋大度と音楽。DJとしての活動、パフォーマンス演出から、楽器制作までその軌跡を語る。

プログラミングやデバイスを用いたメディアアートや映像、ライブ演出などにより日本はもとよりBjorkやSquarepusherなど世界からも注目を浴びるトップクリエイターの一人、真鍋大度。より大きな舞台へと活躍の場を広げながらも、未踏のテクノロジーを斬新なアイデアと結合し、その成果を世に問い続けてきた。その輝かしい功績の裏側には、もちろん、さまざまな試行錯誤や出会いの積み重ねがあった。プラネタリウムの空間でリラックスしながら、そんな彼の辿った稀有な軌跡を聞くことができるレクチャー、「A CONVERSATION WITH DAITO MANABE」が、「RED BULL MUSIC FESTIVAL 2018」のプログラムの一つとして、さる10月3日に行われた。2014年に開催されたRed Bull Music Academyに続き、音楽ジャーナリストの原雅明をモデレーターに迎え、彼と「音楽」の関わりについて紐解いていく。
最初に、スクリーンにはピアノの前に座った少年の写真が映し出された。音楽一家であったという彼の家庭環境について語ることから講義はスタートする。真鍋大度と「音楽」の関わりは、遡れば幼少期にまで至る。小さな頃から作曲やピアノの訓練を受けながらも音楽の道に進まなかったのは商業的な成功と出会えなかったからだそうだが、考えてみれば、その教育がなければ彼の先鋭的かつ音楽的な作品が生み出されることはなかったのかもしれない。そこから話題は大学時代へと時を移るが、当時、数学を学んでいたものの、その知識が表現へと直結することはまだなかった。それよりも、ヒップホップのDJとしての活動に毎日のように打ち込んでいたという。ターンテーブリズムが興隆していた時代背景も大きかっただろう。ヒップホップのDJのように、音楽プレイヤーをこれまでとは異なるやり方で用いて新しい音楽を生み出す。当時は、そんなヒップホップ文化にある初期衝動が彼のインスピレーションの源だった。そしてそのときの経験が、レコードの溝の位置情報を用いて映像をコントロールするIAMAS一年時の作品へとつながっていく。

そのあとに紹介された、音を用いて建物をまるごと揺らすという音響作品も興味深いものだった。建造物が共鳴を起こす周波数を探し出し、その周波数をひたすら奏でるという低音と振動ばかりの凶悪な作品である。またIAMASの卒業制作の作品となった、耳に聴こえない周波数だけを使った曲を作り、それを振動子が敷き詰められた椅子のような形のオブジェに座って体験するという作品にも、同系の発想が見て取れる。音楽への興味から始まり、その可能性を押し広げるような一連の作品は、彼の作品がどのように発展していったのかをより深く知るためのヒントにもなるだろう。
ダムタイプ藤本隆行との出会いは、作曲家、プログラマーの募集に彼が作品を応募したことがきっかけだった。テクノロジーや社会、身体などの関係性をパフォーマンス作品としてコンセプチュアルに表現してきたダンスカンパニーと、真鍋大度という組み合わせは絶妙なマッチングで、それが2004年の時点で実現しているという事実は、今の視点から見ても両者の先見の明を証明している。ここで積み重ねられた、プログラミングや、装置類をパフォーマンスにどのように導入していくかという実験や実践の積み重ねが、その後のELEVENPLAYやPerfumeなどの作品へとつながっていったということは、ここで言うまでもないだろう。

パフォーマンスにおいて、身体と光や映像という視覚的な軸があるとしたら、もうひとつの軸は聴覚、つまり身体により奏でられる「楽器」であるといえるかもしれない。筋電位センサーで筋肉に流れる微弱な電流を拾い、身体の動きに応じて音を奏でる楽器作品や、やくしまるえつこのライブのために作られた9軸の方位や傾きを取得して音や光を放つというオリジナル楽器「dimtakt」、また広告仕事としてはNIKE FREE RUN+を曲げ伸ばしすることによりサウンドが奏でられる装置をHIFANAが演奏したパフォーマンス「NIKE MUSIC SHOE」など、その例は実に多彩である。
また、長い歴史の中で形が定められてきた楽器というプロダクトを手掛けることには、成功も失敗もあったという。モデレーターの原が「自身の作品について楽器として成立したものとしなかったものとの違いは何か」と、質問したとき、真鍋は「練習してうまく演奏できるようになるための『のびしろ』があるかどうか」と回答した。装置が体現するものだけでなく、人間が関わることによる可能性の部分をいかに作り出せるか。その課題の在り処や、困難は、同じ表現者の創造の現場と関わり続けてきた彼ならではのものかもしれない。

真鍋の手掛けるフィールドは、パフォーマンスを彩るための装置や仕組みづくり、はたまた出演者自身がコントロールする楽器から、装置そのものが主体として成立するメディアアート作品まで、とにかく広大である。テクノロジーを基点としつつも、自身も作品を発表するアーティストでありながら、ときにクライントや関わるアーティストの求めるものに答えなければならない。さまざまなカテゴリーが溶け合い、とどまることなく変化し続ける現代の環境において、その特異な立ち位置こそが彼のオリジナリティになっているとも言えるだろう。その原点ともいえる、さまざまなアイデアや出来事に触れられる、貴重な講義であった。

編集者・デザイナー。
兵庫県生まれ。MASSAGE編集長。書籍の企画やインディペンデントでの雑誌の発行など、独自のメディア作りを通して、映像やアート、音楽など創作に関するさまざまな情報を伝えている。
![[Event Report]A CONVERSATION WITH DAITO MANABE──真鍋大度と音楽。DJとしての活動、パフォーマンス演出から、楽器制作までその軌跡を語る。|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)