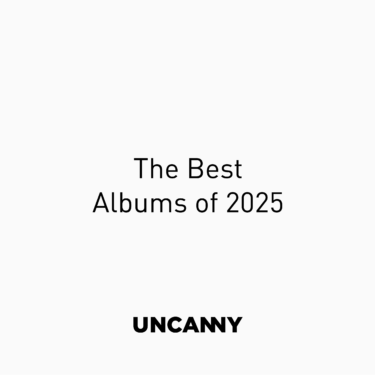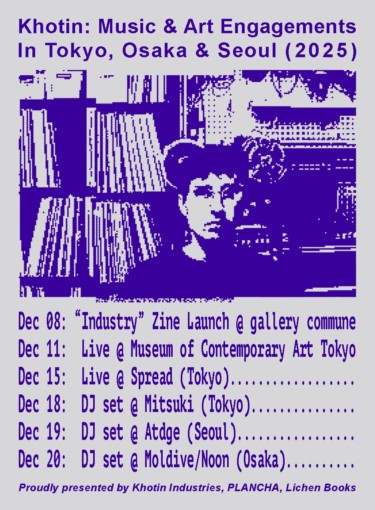- EVENT REPORTSOctober/18/2018
-
[Live Report]“NAZORANAI” – RED BULL MUSIC FESTIVAL TOKYO 2018

2018年9月22日から10月12日まで、約1ヶ月間にわたって開催されたレッドブルによる都市型音楽フェスティバル「Red Bull Music Festival Tokyo 2018」。本稿では、日本の実験音楽界の重鎮、灰野敬二と、USドローン・ノイズユニット、Sunn O)))等の活躍で知られるStephen O’Malley、オーストラリア出身のマルチミュージシャン、Oren Ambarchiによるトリオ、Nazoranaiと、石橋英子によるライブの模様をレポートする。
石橋英子はひっそりと現れ、シンセサイザーの前に腰を下ろした。そしてその不穏でアンビエントな音色をしばし響かせた後に、おもむろにフルートを演奏し始め、さらにリアルタイムでその音を多重録音し、フレーズを重ねていく。マイクに向かい発したおぼろげな声の向こうから、徐々に近づいてくる蒸気機関車の轍の効果音は次第に周囲の音を掻き消し、会場は満州奥地の暗く立ち込める霧の中へと誘われていく。
近年は前野健太のプロデュースや、星野源のバンドでのサポートメンバーといったポップス寄りの分野での活躍が目覚ましい彼女。しかし、そもそもはポストパンク系バンド、パニックスマイルのドラマーとしてキャリアを始め、徐々にソロとして実験音楽界の巨匠たちと共演、最近では特にJim O’rourkeとの共作、共演を通して即興界隈での活躍も目覚ましい。そして、今年リリースしたばかりのアルバム『The Dream My Bones Dream』からの曲を中心とした今回のライブでは、歌と即興演奏の境界を漂う演奏が約30分間にわたって繰り広げられた。
10分間程の即興的な演奏に続いて、シンセの前で歌われたのは中国語の歌詞による「Agloe」。父の死という個人的な出来事をきっかけとして、終戦前後の満州国からの引揚者だった父の記憶、古い写真からの痕跡をたどり、具体音のコラージュといったミュージック・コンクレート的手法と電子音、歌が混然一体となり、一本の映画のように連なる新譜においても重要な一曲である。今回のライブではその演奏はより過激に、後半徐々にアブストラクトな度合いを強め、再び機関車の轍の音とシンセサイザーによる不協和音の律動の中へ、歌は消えていき、残されたのは一音の信号のみ……。
続けてアップライトピアノとシンセサイザーで演奏されたのは「The Dream My Bones Dream」と「Innisfree」。「骨が見る夢」と題されたタイトル通り、死後の世界から響くかのようなおぼろげに響く歌声は、空中を漂い、歪められたシンセサイザーによって奏でられ循環するドローン音と混ざり合い、徐々に歌とインプロヴィゼーションの境界は、現世と死後の世界の境界のように歪められ、その間は消えていく……。そして、突如として訪れた終わり。
今までは実験音楽界と深く繋がりながらも、基本的にソロアルバムでは歌とピアノ演奏を核として形作られていた彼女の音楽が、現在においてはよりポップスと実験音楽の境界を曖昧に、同じくミュージック・コンクレートといった実験音楽的な手法に傾きつつも、独自のポップミュージックを作り続ける近年のLaurel Haloにも迫る存在感を持って、会場を支配した30分間であった。そして、そもそもそれは活動当初からどこにも属しきらない彼女の特殊な立ち位置を雄弁に物語る、その本質を露わにする演奏だったと言えるだろう。

そして、同じくその実験音楽界において、世界にまで広範な影響力を誇る灰野敬二とStephen O’Malley、Oren Ambarchiによるトリオ、Nazoranai。この形態では約4年ぶりとなる来日公演は、約1時間半にわたって嵐のような静と動が交錯するインプロヴィゼーション、その言葉自体を嫌う灰野によれば“なぞらない”そのものだった。
ノイジーにギターをかき鳴らす姿がトレードマークの灰野が、最初に持って現れたのはなんと巨大な縦笛。フヤラというスロバキア地方に伝わる自分の背丈の倍以上ある笛を操り、朗々と奇妙なフレーズを奏でる灰野に寄り添い、ベースのStephen O’Malleyは淡々と短い重低音を響かせる。そして、さらに灰野は小さい縦笛、フルートと楽器を持ち替えていき、嵐の前の静けさのような奇妙な空気感の中、ようやく声を出し始めるが、やがて再び笛を演奏し始め、マイクにハウリングさせたその甲高い悲鳴のような音響が会場中に響き渡った。そして、ドラムのOren Ambarchiも加わり、リズム隊によるパルスビートが灰野の後を追い始めると徐々にテンポはアップ、次第に演奏は白熱し、灰野がノイズギターを奏で始めるまでに何分経ったのだろうか。その後は不失者とSunn O)))が重なり合ったドローンメタルと形容できそうな強烈な轟音が辺りを支配し、約10分間。これが“なぞらない”である。

1978年から不失者という特異なロックバンドを開始し、以後約40年間にわたってノイズ、ロック、ミニマリズム、ドローン、インプロヴィゼーション界隈において世界的な影響を与え続ける、灰野敬二。そして、彼からの影響を公言する同じくノイズ界の重鎮、Stephen O’Malleyと、エクスペリメンタル/インプロヴィゼーション界で暗躍するOren Ambarchi(灰野とはJim O’Rourkeと共にトリオとして即興演奏を重ね、アルバムも出している)。この三者の邂逅によるNazoranaiこそ、灰野敬二の本質をある意味では現在、最も如実に表している編成ではないだろうか。
その後もNazoranaiは、灰野の鋭いカッティングギターが唸る高速ブルース調の曲を演奏したかと思えば、シンセサイザーによる循環ドローンの上で灰野がインドの弦楽器、ルドラヴィーナをLaraajiをも彷彿とさせるスティック捌きで一心不乱に演奏する瞬間などもあり、縦横無尽に灰野はリズム隊の上で動き回る。常に自己探求の果てに自己からの逸脱を志向し、過去を“なぞらない”ことこそが、灰野敬二の活動だった。

デビュー・アルバムを出すに当たり、周囲からの期待を裏切ってノイズアルバムではない、即興的なブルースを意識したレコードを製作し、その後も何十種類もの楽器に習熟し (時には「experimental mixture」名義でのDJ活動も行う)、そして自身を最も分かりやすく形容するとすれば、「グレゴリア聖歌とカントリー・ブルースの融合」と嘯く(1)。ここ2年以内のアルバムを振り返ると、インプロ界隈の大家John Butcherから、トルコのフリージャズ集団Konstrukt、日本の若手Musqisに至るまで、特にコラボレーションに精力的でその創作意欲は衰えを知らない。黒と白、聖と俗、自己と他者……相対するものとの対峙により追求するのは、自分自身の自分自身によるアンチテーゼ。その絶え間ない否定の先に目指すのは、消失点の向こう側にある「完全な自由」か。そんな途方もない探究心こそが灰野敬二を今も突き動かす原動力であり、今なお更新され続ける迷宮のようなディスコグラフィでファンを実験音楽の深みへと誘い込み、USアンダーグラウンドの巨人Thurston Moore (特に初期Sonic Youthにその影響の片鱗が見える)や、Stephen O’Malleyといったミュージシャンに今なおリスペクトされ続ける存在となっている理由ではないだろうか。
そして、即興的な灰野の行為がギリギリのラインで耳に留まり、独特な緊張感を持ったフリー・ミュージックとして成立しているのも、幾多もの共演を重ねたOren Ambarchiの音の狭間に的確に鋭く突き刺さるドラミングと、モダン・ドローンのベテランStephen O’Malleyが操る熟練した重低音ベースによる支えがあってこそ。この三者の間に構築された独自の力学が作り出す緊張感、常にそれに駆動され演奏は徐々に終盤へ。灰野が作り出すノイズの壁、その向こう側で地を蠢くベースとドラムは最大音量となり、これで大団円……と、思いきや再び最大から最少へ。歌とも呻きともつかない単音で繰り返される声、声、声……。最後は灰野による縦笛のソロ演奏で締めくくられた。やはり、最後までこちらの予想を裏切ってくるのが、灰野の美学である。
(1)…#156 灰野敬二:デビュー・アルバム『わたしだけ?』を語る http://jazztokyo.org/interviews/post-16171/

1992年生まれ。得意分野は、洋楽・邦楽問わずアンダーグラウンドから最新インディーズまで。
![[Live Report]“NAZORANAI” – RED BULL MUSIC FESTIVAL TOKYO 2018|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)