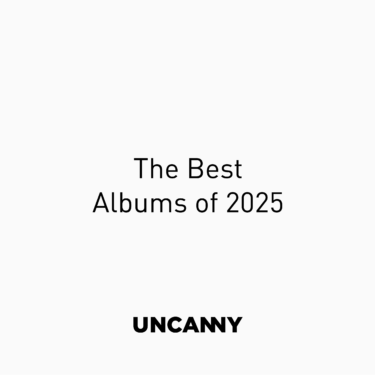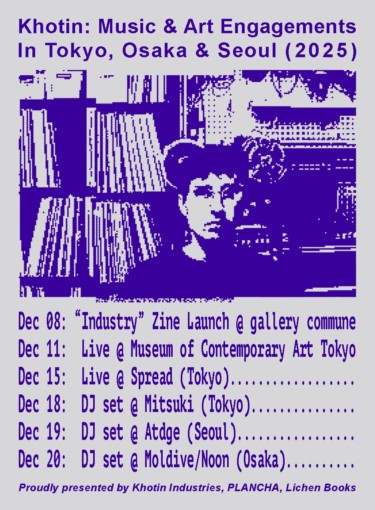- ARTIST:
-
Low
- TITLE:
- Invisible Way
- RELEASE DATE:
- 2013/3/13
- LABEL:
- SUB POP / TRAFFIC
- FIND IT AT:
- Amazon
- REVIEWSApril/16/2013
-
【Review】Low | Invisible Way
シンプルなものほど、多くのものに縛られる必要がなく、内面的に豊かで在りえるのではないだろうか。偽物かもしれない等価交換に頼って、本当は存在さえ怪しいそのものの価値に疑問を抱くこともなく生活を送る現代の我々には、その実践も、人によっては理解すら難しい。何故なら消費は快楽であり、現代人は生まれた時からその欲望を刺激する装置で周りを囲まれているからだ。
Lowの音楽は、アメリカナイズされ、フィクションの等価交換の虜になり消費を繰り返す私たちの暮らしに、ソローが描いたような贈与と返礼によって成り立つ象徴交換を基盤とする森の暮らしの情景を見せてくれる。自然の緑の濃淡や空の自由さ、外面よりむしろ内面の力強さが彼らの音楽から浮かび上がってくるのだ。
スロウコアの巨匠としてその名を知られるLowというバンドは、当初は92年に解散してしまったバンドSlintを思わせるようなミニマルでドリーミーな雰囲気が漂う曲を多く演奏していた。4枚目となる、1999年リリースのアルバム『Secret Name』よりアコースティックギターに加えてヴァイオリンを多く使い始め、バンドはより壮大な世界観へと向かって行く。<SUB POP>と契約後の2005年リリースの『The Great Destroyer』と2007年リリースの『Drums and Guns』は、The Flaming LipsやMogwaiの仕事で知られる、インディ・ロック、ポップを得意とするDave Fridmannをプロデューサーに迎えて制作された。そこで、Fridmannはそれまでの楽曲の持つ影の部分を際立たせ、エレキギター中心でよりロックらしい構成の、泥臭いサウンドづくりを行った。2011年リリースの前作『C’mon』はDave Fridmannが担当した前2作品のアルバムの反動として捉えられることができる作品だ。そのことは『C’mon』を制作するにあたって、バンドが2002年リリースの『Trust』をレコーディングした木のぬくもりが残る古い教会で再びレコーディングをした事実や、エレキギターよりもアコースティックギターを多用した収録曲等から伺える。とにかく、こうしてアルバムを重ねるごとに、私たちは様々なLowの音楽を聴いてきた。
今回の新作『The Invisible Way』は、バンド結成から約20年となる記念すべきアルバムだ。本作は、リリース前から、普段から親交が深いというWilcoのJeff Tweedyがプロデューサーを務めたことでも注目を集めていた。結果的に、この組み合わせは成功している。Wilcoの持つ、温かみのある明るさやすべてを許すようなポップさが、Lowが本来持つ、うつむききがちな暗さや海底を思わせるような深い悲しみと混ざり合い、曇り空から太陽が注ぐような神秘的な音楽をつくりだしているのだ。
しかしながら、新作『The Invisible Way』を彼らの20年間の集大成のアルバムと呼べる理由は、プロデューサーであるJeff Tweedyの働きのおかげだけではない。例えば、「So Blue」のピアノの奏でる強弱が生み出す躍動感や、聖歌のような神々しさを感じられるハーモニーワークは教会でレコーディングを行ったアルバム『Trust』を彷彿とさせ、「Clarence White」はバスドラムと手拍子のミニマルなリズムとアコースティックギターとベース、ピアノの音のみの構成で演奏されているにも関わらず、まるでオーケストラが演奏しているかの様な壮大さと迫力を持ち合わせており、ヴァイオリンを多用したアルバム『Secret Name』を想起させる。そして、「On My Own」のアコースティックギターからノイジーなエレキギターへの展開は、Dave Fridmannの担当した『The Great Destroyer』や『Drums and Guns』で得たサウンドからの延長線上にあるものだ。
このように、新作『The Invisible Way』がバンドの集大成のアルバムであると言えるのは、楽曲の至る箇所で20年のLowの歴史が生きていることが聴きとれるからだ。この作品は、これまで彼らが奏でてきた音楽が、雨のように土に染み込み、そこに新しい芽が誕生したようなアルバムなのである。
そして、『The Invisible Way』は、全曲を通してピアノやアコースティックギターの生音を基調にして作られており、はっきりとした強弱の差や、クラシックオーケストラさながらの躍動感が聴く者を決して退屈させない。その上、生音特有の暖かさが伝わってくる仕上がりになっている。
エフェクターを多用し、練りに練られた音が重なり合っている楽曲や、クラブミュージックからの影響を受けシンセや打ち込みを多用する楽曲が主流の現在のインディ・ロック・シーンにおいて、本作はその流れとは全く異なる作品だ。しかし、そのシンプルな楽器構成こそが、彼らの音楽に自然から得られるようなぬくもりと豊かさを与えているのだ。
文:永田夏帆
1992年生まれ。UNCANNY編集部員。趣味はベースと90年代アメリカのポップカルチャー。青山学院大学在籍の現役大学生。