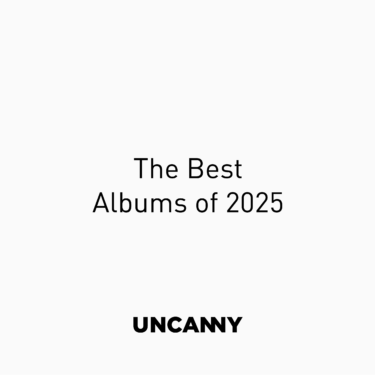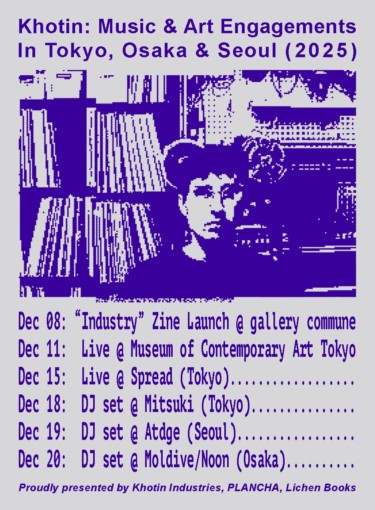- ARTIST:
-
tofubeats
- TITLE:
- First Album
- RELEASE DATE:
- 2014/10/2
- LABEL:
- Warner Music Japan
- FIND IT AT:
- First Album(初回限定盤), First Album(通常盤)
- REVIEWSDecember/10/2014
-
[Review]tofubeats | First Album
「残念」な、「良さがある」
おそらく現在tofubeatsを語る(そしてtofubeatsのインタビューを読む)ということは、今の音楽を語ることと、さらに拡大して今そのものを語ることとニアリーイコールな状況になってしまっている。今作は、インターネット/ポスト・インターネットから現代の音楽産業、はてはクラブ問題や関西シティ・ポップまで含めて、あまりの多くのキーワードを背負わされながら、本人もそこを引き受けつつも、そのままフィールドをメジャーシーンに移して、大物アーティストの起用など願望を現実化し、フロアにもJ-POPにもそれぞれの曲が対応しているという彼の天性のバランス感覚が遺憾なく発揮された作品だ。
ポスト・インターネットといえば同じく、今年出た本の中で最も興味深いキーワードを出した本の中にライター・評論家であるさやわか氏の『一〇年代文化論』(星海社)がある。この本の中で著者はここ数年に起きた文化現象(アニメ・アイドル・インターネット)の中に頻出する「残念」というキーワードを中心に、その言葉の使われ方がいかに変わっていったかを叙述していくのだが、例えば「残念な美人」(例えば、美人なのにオタクであったりした場合)という言葉に対して
①一般的な理解・・・「残念」(短所)+「美人」(長所)
②ニコニコ大百科の解説・・・「残念+美人」(長所)
というように、前者のそれは「美人」の要素を「残念」な要素によって無駄にしている、といったようなニュアンスを含んでいるのに対して、後者は「そういった欠点も認めた上で、それらを肯定する」ようなニュアンスを含んでいる、ということらしい。らしい、というのはここあたりの議論は非常に抽象化されていて、我々はその微妙なニュアンスの違いを感応するか否か、という事を迫られているというまさに変化の途上にある言葉を探っていくスリリングさがあるのだが、これを読んで思い出したのはtofubeatsのことだった。
tofubeatsは自身がボーカルをとる際、かならず「音程補正ソフト」であるオートチューンを使用して歌う。それは本人が自ら「歌唱力がない」と言っているような「残念」な要素であるのだが、むしろ聞き手達は彼のそういう「不完全」な要素を見ることで、一見非の打ち所のないようなサウンドプロダクションの中で、一番機械的に変化された「声」に、むしろtofubeats自身のある種の親しいパーソナリティーを感じて応援してしまう。冒頭二曲目の「#eyezonu」が、新進ラッパーなら勢い良くセルフボーストをかますような場所で、むしろ体調の悪さや家に「出て行かない」ことをラップし歌う(ここで、「調子悪くて当たり前」を出すのはちょっと古いか)また、「poolside」PVにおけるtofubeatsの立ち位置など、本人のディレクションがないにも関わらずその「残念」な感じが確固として共有されているのがわかるだろう。同じ「女の子」「クラブ」「インターネット」を題材に多くしている、今年を代表するラッパーであるKOHHがフィーチャーされたDJ SOULJAH 「aaight feat. KOHH & Maria」などを比較すると、同じ題材なのにここまで描き方が違う!(当たり前だが)と思うだろう。
一方でtofubeatsに関連して使われる言葉に「良さがある」という言葉がある。これはTwitter上から発した「糸井重里bot」の発言を、伊藤ガビン氏が面白がり、tofubeatsの「No.1」のPVについて取り上げる際にこの言葉を使ったことで(modern fart | よさについて tofubeats No.1 feat.G.RINA 監督インタビュー)波及し、SNSを中心に周りの人達にも広がりを持つようになる。例えば〇〇を褒める場合に、「〇〇が良い」ではなくて「〇〇良さある」といったように。
これら違う2つの言葉が、同じ現象を基に変化してるのではないかと自分は考える。これはまさにあらゆるものが情報化された後において、従来的な言葉の持つベクトル・指向性といった力学がうまく働かなくなっている現在。例えば「オタク」という言葉。今でもこの言葉をアイデンティティにしたり、対立を煽るような言葉として使用されているが、その時対比されるのは場合によりまちまちで「vs リア充」であったり「vs サブカル」であったり「vs 普通の人(表現規制などの議論で)」だったりする。ここまで来ると「オタク」という言葉が指し示すものがなんなのか、まるで否定神学じみてしまうのだけれども、実のところ、もはやそういった対立構図などというものはほとんど存在せず、コンテンツの中にオタク性もサブカル性もリア充も存在しており、それらは別に他者と自己を分けるような分水嶺になりえないという状況をむしろ表している。現実に今の10代は普通にボカロを聞き、それとロキノン系バンドやアイドルを聞いているのだし、毎週アニソン系のクラブイベントやアイドルのイベントに足繁く通う人々を従来通りオタクと呼ぶと若干の違和感もある。それはコンテンツのマッピングを基に「ここからここまでがオタク」といった示し方よりも、ニコニコ動画のタグ付けのように「#オタク」や「#サブカル」が付いている感覚、さらにそこに「#残念」や「#良さ」が並列に付けられている感じを想像すれば、なんとなくは分かってもらえると思う。なにせ現在の音楽系SNSは「#seapunk」や「#vaporwave」など、「先にタグ付けされてからジャンルのイメージが確定される」ような、そういったタグ付けを基にジャンルを発展させるといったような現象もあり、もはや「そんなの当たり前だよ」と思う人のほうが多いのかもしれない(もっと言うとこの「指向性のなさ、マッピングの不可能性」の概念を政治にまで拡大して考えると、いろいろ思うこともあるのだけど、それはあまりにも議論として脱線が過ぎるのでここでは触れない)。
なにはともあれ『First Album』だ。tofubeatsのメジャーデビュー初のアルバムであり、10月2日(トーフの日)に発売された今作は、そういったポスト・インターネット的な感覚をそこかしこに見ることのできる作品になっている。今作で最も「残念」という呼称が似合うであろう楽曲は、LIZをフィーチャーした「CAND¥¥¥LAND」だろう。ハイエナジーというか、ユーロビートが日本に輸入された80年代(高護『歌謡曲』によると、ユーロビートは当初日本でオリジナルなサウンドが作られずに、荻野目慶子、WINKなどがそのままカバーするといった方法から、船山基紀が留学し、和製オリジナルユーロビートを「仮面舞踏会」で確立、その後に筒美京平が中山美穂作品によって完成系を示し、その路線を角松敏生が引き継ぐという流れで「輸入→留学→オリジナル」という近代化の過程を短縮化したモデルのように叙述している)から、90年代に日本の「手踊り」の要素を持ち込んで「パラパラ」となっていった過程は、そのまま「当時先鋭だったものがドメスティック化され陳腐になっていく」殘念化そのものだった。そのパラパラを20年経った後に取り上げ、しかも外国人であるLIZとコラボレーションするというのは、文脈が二重三重に錯綜しているが、シンプルに聞くと「良さがある」としか言いようのない、しかしちゃんと殘念な要素もあるという楽曲になっている。例えばこれと対称的なスタイルとして、ネイティブな英語話者が日本語ラップをするSarah(Kero Kero Bonito)と、謎の日本文化政策ゲリラアーティスト©OOL JAPANとラブリーサマーちゃんとのコラボ「Rush Hour」を比較して聴いてほしい。
そもそもパラパラに関して言うならば、その手の細かい振り付けに対して、足のステップは左右に1,2,1,2と振れるだけというシンプルなものに変化している。このリズムの単純化はドメスティック化の端緒といったようなもので、J-POPにおいて曲が「1,2,3,4とアタマ拍で取れる」ことが必須となっている。それはメロコアのヘッドバンギングから現在のヲタ芸に至るまで通底しており、常に2.4拍やウラ拍を強調するブラックミュージックを日本でやる際に直面する問題なのだが(例えば、山下達郎の諸作品をそういう戦略の基に聴いてみてほしい)、tofubeatsの場合、彼は自然とバックビートを基調としたリズム感を元々に備えているタイプで、むしろ縦ノリの刻み方を苦手とするということを自分に語ってくれたこともあるが、そんな彼がJ-POPのフィールドで勝負をかける際に、パラパラや、シングルでの「四つ打ち」や「ディスコ」を提示し、ちゃんとJ-POPとして成立するプロダクションを行っている所も注目したい。同じ「ディスコ」を題材にしている「ディスコの神様」とパジャマパーディーズ「mp3」のtofubeats discojam remixを比較して聞いてみると、彼がもっと感覚的にリズムを打ち込むとバックビートが強調され、かつウラ拍に奇妙な浮遊感をもたらす、まるで後ろ向きにスキップするような独特なグルーヴ感があるのだが、その感覚を保ったまま、J-POPとして成立するバランス感覚に舌を巻く。
中盤怒涛のインスト群「pupuluxe」〜「content ID」の流れからは彼の最近のインターネット音楽の流れや、副アカウントでの活動の反映として聴くこともできるし、「populuxe」ではポリリズムにも挑戦している。そういえば今年CDリリース、メジャーデビューをした同じく関西のSugar’s Campaignもカップリング「香港生活」でポリリズムを強調するようなパートがあった。
そして、newtownやベッドタウンから、街の喧騒を憧憬して見るような「way to yamate」(快速によって引きはなれれていく街。遠ざかっていく音楽は全てブルースに聞こえる)、Bonnie Pinkのボーカルによって一層曲の芯が太くなった「衣替え」。宇多田ヒカル「For You/タイム・リミット」へのアンサーソングのような「ひとり」を経て、ラスト「20140803」へと至る。
アルバムの最後を飾るナンバー「20140803」。本人監督によるPVではシンメトリーな本人のラップする映像の後ろで、平行して流れる景色(おそらくは電車からの景色で彼が中学から通った阪急電車からのものだと思われる)と共に、「高校時代のWIRE初出演時」「彼が楽曲制作をしているエイブルトン(ちゃんと落ちる。#ありがとうableton)」「歴代の楽曲PV(水星撮影時のスケートボードで転ぶといったNGシーン)」や「本人演奏のベースとギター(ベースは彼が音楽を始めようとした際に購入しすぐ挫折した楽器、ギターは最近購入し、練習したという)」「クラブ会場の客席」の映像がカットアップして流れていく。過去から今に至るまでの道程をバインドしたようなこの曲で歌われている「音楽があればいい」という明確なメッセージはこれから音楽をやりたい人たちへの励みとなっていくだろうと思わせる。
また、当然ながら冒頭曲「20140809」と比較すると、こちらの日付が過去にあるということもわかるだろう。これはつまりこのアルバム自体がブログやTwitter、Tumblrなどの「最新のものが一番前に来て、過去のログほど後方にくる」タイムラインの構成になっているのだ。つまりこの曲はアルバムのラストナンバーであると同時に「所信表明」でもあるという意味を持っている。また、リリース日(10月2日、トーフの日)と時間の差を日付タイトルによって強調し、「アルバム制作の納期」と「リリースまでの過程」を強調するあたりに、リリース前のフルストリーミング視聴や、彼のネット時代からの「過程を見せていく」というアプローチが伺えたりもする。
例えばこのtofubeatsのインスト群と歌モノの差異化に関して、かつてJ-POPをダンスミュージック化させたdj newtownのように、「クラブを意識したインスト群のようなサウンドのJ-POPを聞きたい」という意見もあるだろう。2008〜10年ごろの中田ヤスタカが、(おそらく過剰な生産ペースで、本人もどっちを作っていたのかよくわからなくなっていたのだと思うが)どんどんこの2つのジャンルを融解させたような楽曲をリリースしていったように。そういった期待も込めつつ、2014年という現在をパッケージングした一枚として後々の世代までこの『First Album』が聴かれることを強く願う。
文:神野龍一
1985年生まれ。「関西ソーカル」をオノマトペ大臣と共に主宰。音楽だけではなく、文学や思想などにも興味あり。執筆依頼募集中。
![[Review]tofubeats | First Album|UNCANNY](https://uncannyzine.com/wp-content/themes/uncanny_v6/common/images/logo.svg)