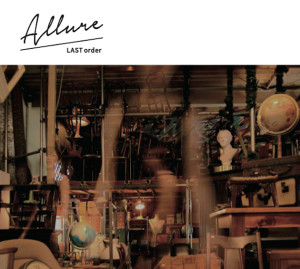
- ARTIST:
LASTorder
- TITLE:
- Allure
- RELEASE DATE:
- 2014/7/10
- LABEL:
- PROGRESSIVE FOrM
- FIND IT AT:
- Amazon
- REVIEWSJuly/25/2014
【Review】LASTorder | Allure
巷の流行は20年周期で繰り返されるのだという。諸説あるにせよ、例えば、流行となるファッションの引き出しには当然限界があり、全く新しいものが常に提案されることは珍しい。過去を参照すると、飽和しきって、乗り越えたはずのファッションデザインの歴史から、驚くべき新鮮味を持って登場するものがある。そういったものが発掘される周期が大体20年間であるという。20年という根拠は、一世代の交代にかかる時間がおよそそれくらいであるから、というのがそれなりに説得力をもつ考えとして提示出来るかもしれない。その考えを大真面目に受け止めるとするなら、僕たちは現在、大体1994年のそれと似通った光景を毎日目に焼き付けているのだろうか。iTunesにスマートプレイリストを立ち上げ、「1994年」でソートしてみる。FISHMANSが検索に引っかかる。そういえば最近、パーティの終盤にFISHMANSを聞くことも多くなったような気がする。僕が1〜2歳だったころにリリースされた「Go Go Round This World!」や、「いかれたBaby」といった曲を、今現在僕たちは当然のように享受し、まるで自分事のようにその歌詞に込められたメッセージを胸に抱く。
90年代はそれはそれはCDがとても売れる時代だったのよ、と色々な人が、様々なメディアが言う。今や音楽の消費は分散され、媒体の価値が変容し、何万という人間が数千円を出してまで手に入れたいCDというのは希少になってしまった。僕たちも、CD自体の売上というものよりも、CDを出した偉大さや、アーティストの価値そのものを値踏みするようになった。今となってはアーティストを直接支援する方法なんていうのはいっぱいあるので、CDの売れ行きがどうであろうとさほど関係はない(しかしレーベル側は当然冷や汗ものである)。ここからの展望に希望はあるだろうが、産業は縮小し、当時の栄光は影しか残っていない。それでも作品が残り、中古店や図書館に並び続けているのは、逆にCDが物体であるという利点が生かされた皮肉のように思える。それでも、今でもCDが、更にはレコードまでもが変わらず出荷され続け、その消費サイクルを繰り返し続けている。このサイクルは、産業そのものが20年来の復権を願って繰り返している願掛けのようなものかもしれない。
2014年7月、日本の電子音楽レーベル〈PROGRESSIVE FOrM〉から満を持してリリースされたLASTorderの2ndCDアルバム『Allure』。1993年早生まれの彼は、2013年に1stアルバム『Bliss In The Loss』をリリース。19歳までの頃に制作した音源を収録したそのアルバムは、その年齢で括るには非常に完成されていて、日本の新たな才能の登場を疑う者は誰も居なかった。その後、Kaigen x Shing02「自描く」のサウンドプロダクションや数々のリミックス、ポスト・ロック・プロジェクト「The Wedding Mistakes」(これは紛れも無く、僕が誇るべき、MiiiとLASTorderによるプロジェクトである)の結成を通過し、Bandcamp上でミニ・アルバム『Unreal Dialogue』をリリース。無料で公開されたこの作品集では、『Bliss In The Loss』から更に深みへと飛び込み、早熟に早熟を重ねたLASTorderの耽美なサウンドが堪能出来た。それから一年あけず、今作『Allure』のリリースとなるのだから、彼の多作ぶりには驚いてしまう。そして間違いなく、下馬評と違わず、このアルバムが彼の現時点の最高傑作であることについては僕も否定しない。
その1曲目「喪失 feat.秦千香子」のメロディーラインは、驚くほどにJ-POP的で、それ自身が感情の繊細な部分を突いてしまう程の破壊力を持っている。『Allure』には「喪失」の他にも2曲目「Abdication feat.Annabel」、6曲目「Temporary Sympathy feat.Piana」といった非常にメロディアスなボーカル曲が連なる。中でも、アルバム内で最長の曲尺を誇る「Temporary Sympathy feat.Piana」は、前半の展開はポップスを踏襲しながらも、後半はミニマル的な音の展開を見せ、Pianaの透明感のある歌声のループと僅かなストリングスを残してフェードアウトしていく、間違いなくアルバムの山場と言える壮大な楽曲である。
今作には、LASTorderのポップスのセンスを遺憾なく発揮する楽曲群に加え、過去のアルバム『Bliss In The Loss』や、『Unreal Dialogue』のような、耽美なカットアップとヒップホップ的なビートが交差するビートミュージック的な音楽も多く収録されている。彼の豊富な音楽教養に裏付けられたLASTorderのカットアップ・サウンドは、荒々しくも神秘的な独特の哀愁を持っていて、Shing02が彼のサウンドに強く感銘を受けた話も頷ける。不規則にカットアップされたボーカルには魂が吹き込まれ、その手法は9曲目「Isolation」や11曲目「New Moon Addict」等のアルバム後半の楽曲に顕著である。特にアルバム最終曲の「Beautiful」は、カットアップされたボーカルに新たな歌心が宿ったような気迫ある楽曲であり、ビートも、それにゆっくりと被さり、静かに冷たく鳴り響いている。
LASTorderの楽曲は、ビートミュージック的な位置に着陸しながらも、非常に繊細なシリアスさ、そして今作ではこれまでのLASTorderのヒップホップ的とも言える反復から少し逸脱し、ポップス的な展開やメロディーラインまでも兼ね備えるようになった。『Allure』全体の物寂しくも神秘的なサウンドテクスチャから覗えるのは、言うなれば退廃的な耽美、息の詰まるような美しき対象である。そういった対象とは、現代的ではない何か、例えば、LASTorderが愛して止まない90年代、そして世紀末のオーラである。彼とは時々プライベートを共にすることがあるのだが、飲みの場を開けば、彼が創り出すその耽美なサウンドとは対照的に、飯島愛、ギャル文化、ケータイ小説等といった、非常に大衆的で、ある意味退廃的な話題が常に飛び出すものだった。90年代。J-POPという音楽が登場しだした時代、バブルが崩壊し、僕らのよく知る不況が訪れた初期の時代、停滞した空気が張り詰める世紀末の厭世観、それは過去のものであると同時に、僕らには到底辿り着けない対象でもある。LASTorderにとっては、それは懐かしき追憶の対象というよりも、羨望の対象であるのかもしれない。
冒頭の話に戻り、流行が20年の周期で繰り返されているのであれば、僕たちが今「1994年」の光景を見ているのであれば、僕たちの感覚は、再び「世紀末」の厭世観に突入するのではないだろうか。モニターから目を外に向ければ、少しずつ世相は不穏な方向に向かっている気がしないでもなく、ニュースはやたらと異常気象を取り上げたがる。享楽的なサウンドの流行は、ポップスの商業化、形骸化に作用し続けている。これがあと5年経てば正常に戻る見込みも恐らくない(そもそも正常とは何を以って正常と言えるのか?)。そんな中で、LASTorderが見つめ、憧れる世紀末的情景は、いずれ未来のそれと重なり始めるように思えてならない。そういう意味で、『Allure』で提示された、驚くほど繊細で、神秘的で、閉塞的なポップスは、過去へと向けられた羨望した追憶であると共に、次世代へと鳴り響く音楽でもあると、彼の才能に対する希望的観測を含めて断言したい。5年後の世界が、果たしてどんな感触をもって僕たちの目の前に立ち現れるのだろう。そんな中で、今書いているこの預言書の答え合わせを、また飲みの席で行うことが出来れば、というのが僕の数少ない願望の一つである。
文・和田瑞生
1992年生まれ。UNCANNY編集部員。ネットレーベル中心のカルチャーの中で育ち、自身でも楽曲制作/DJ活動を行なっている。青山学院大学総合文化政策学部在籍。


